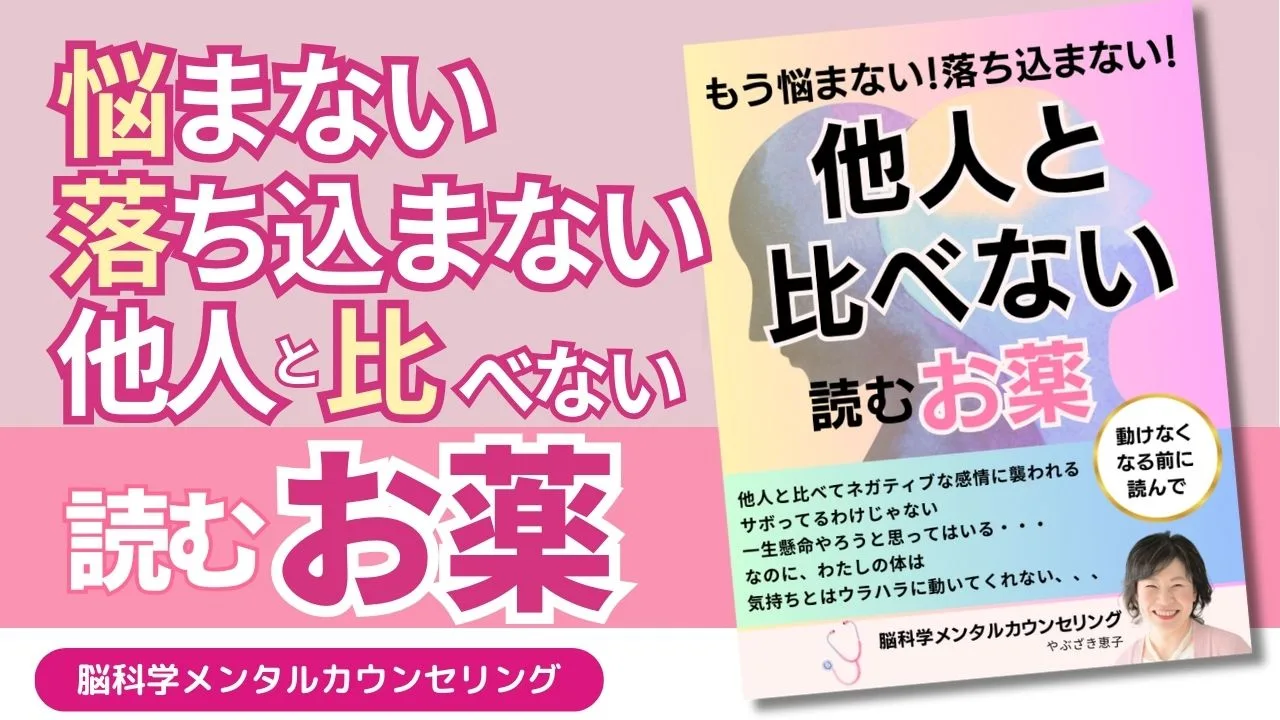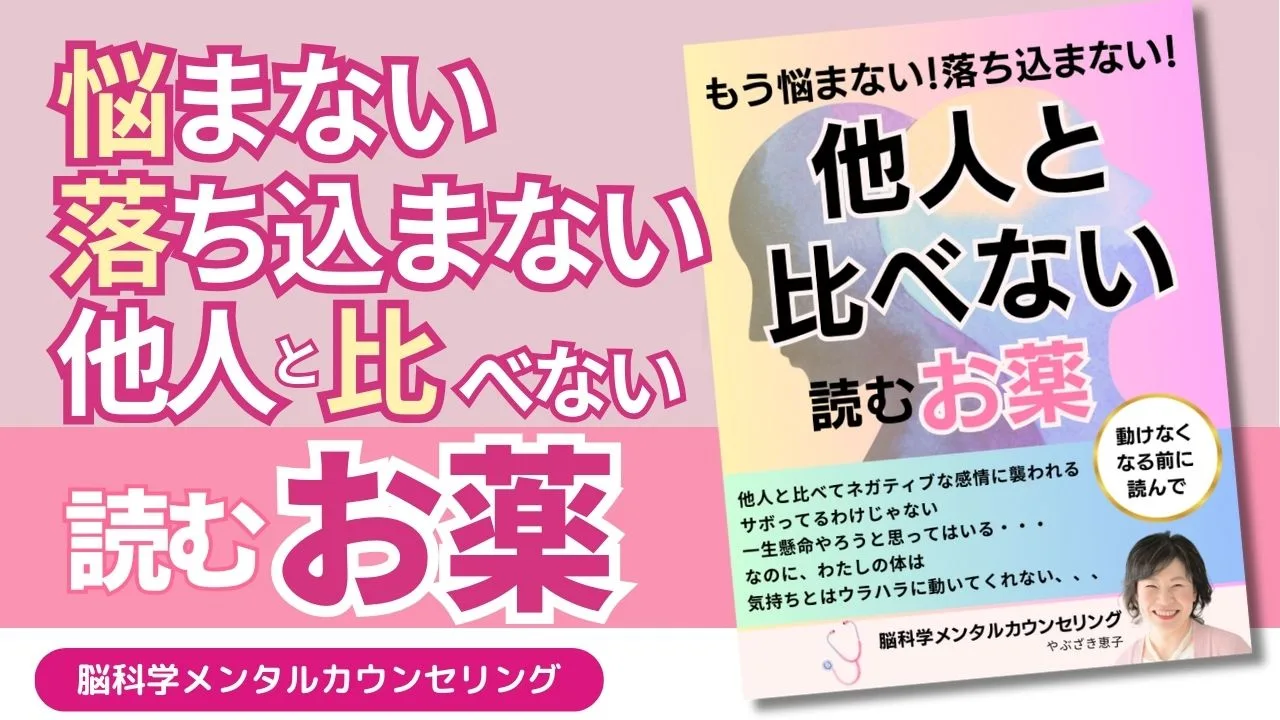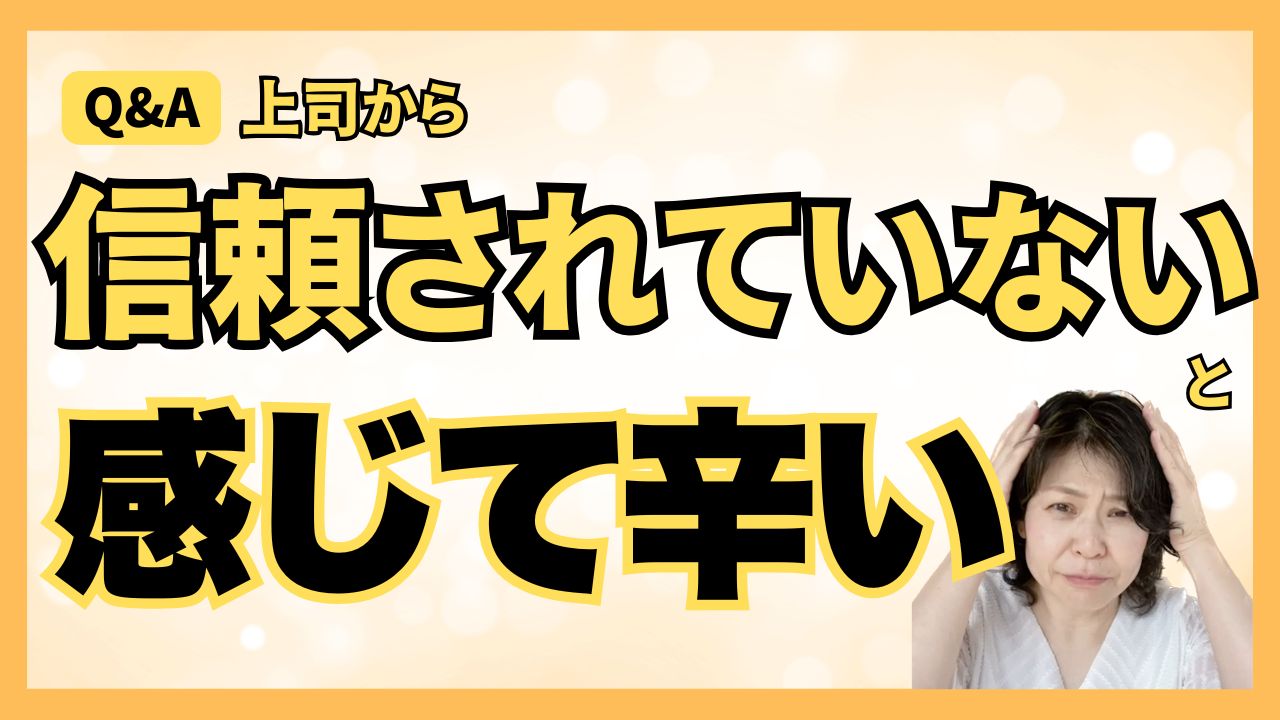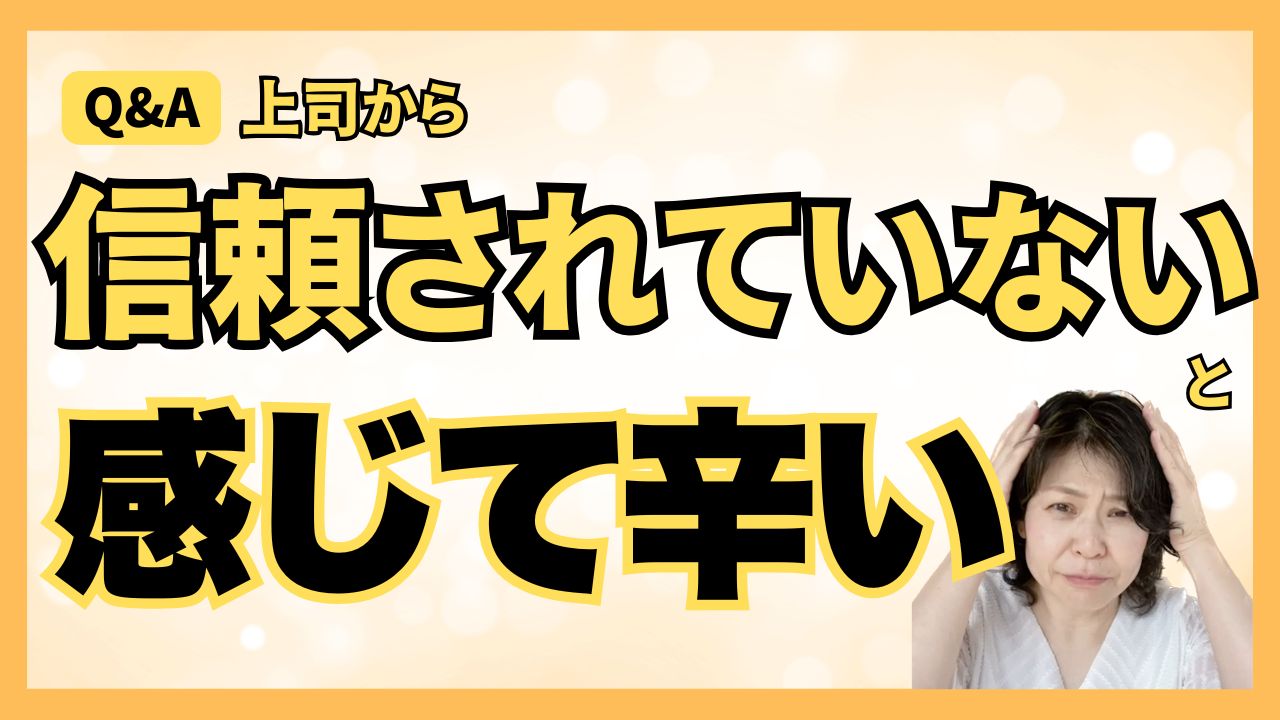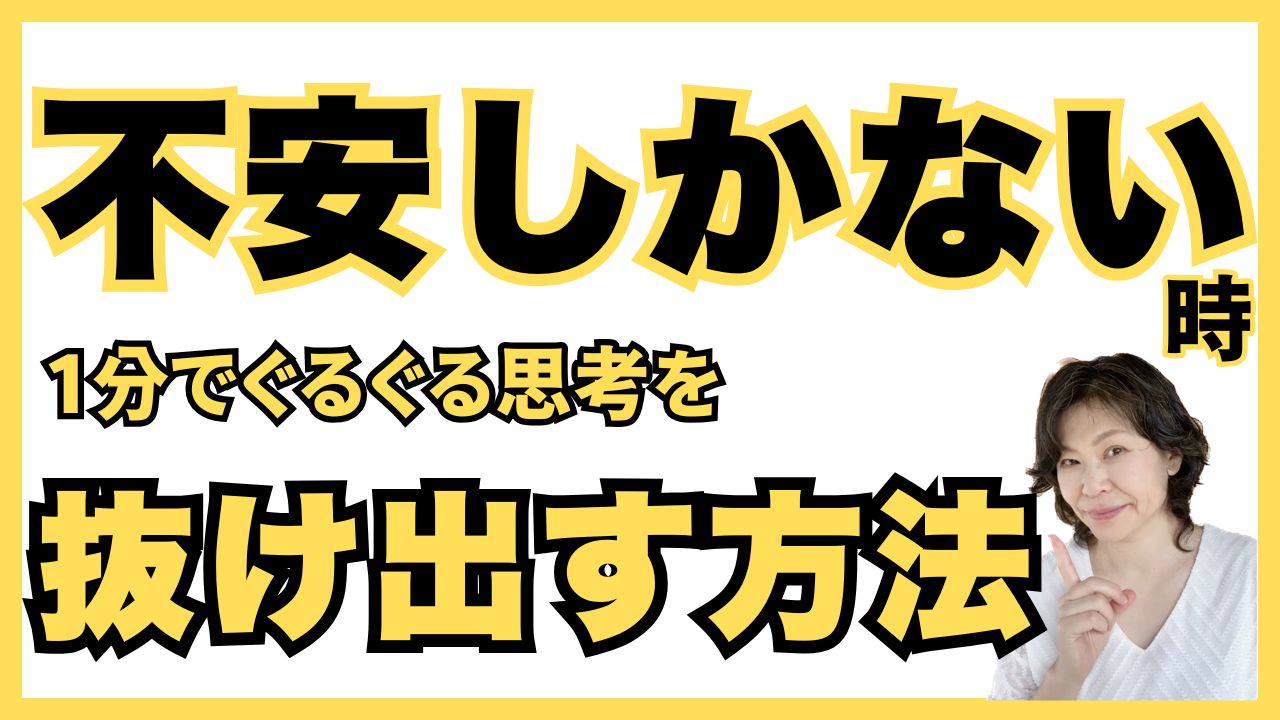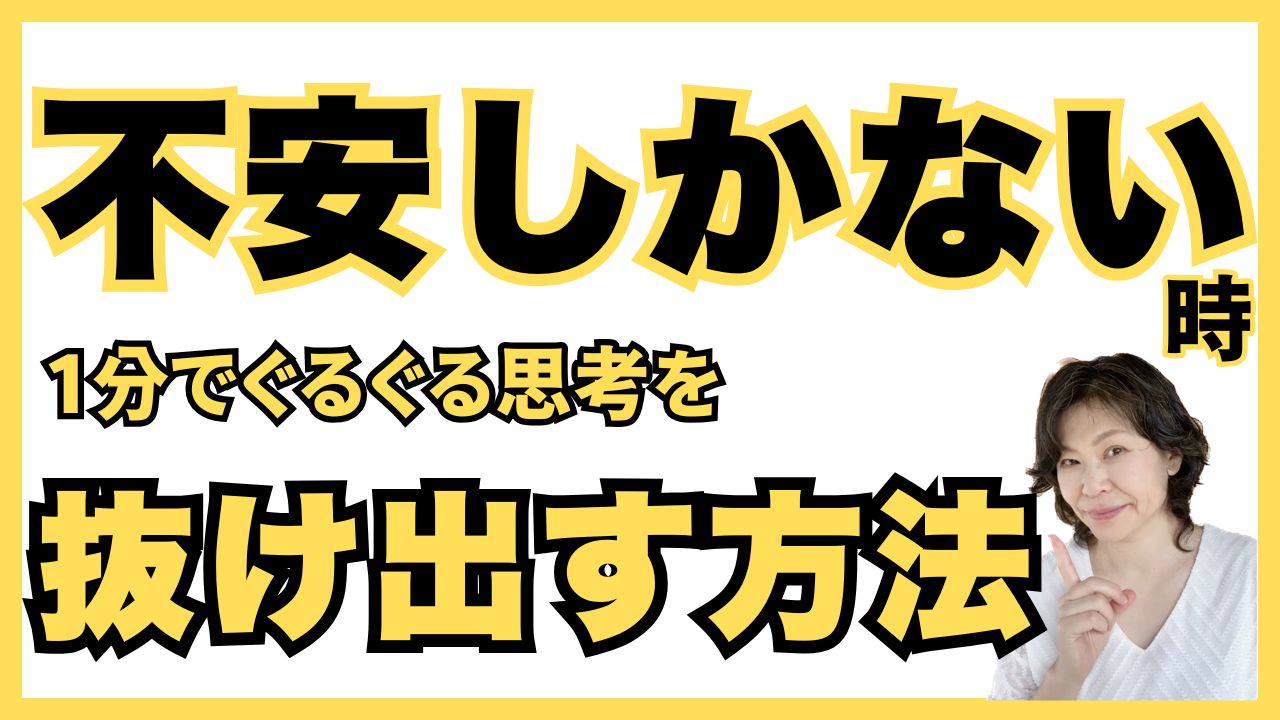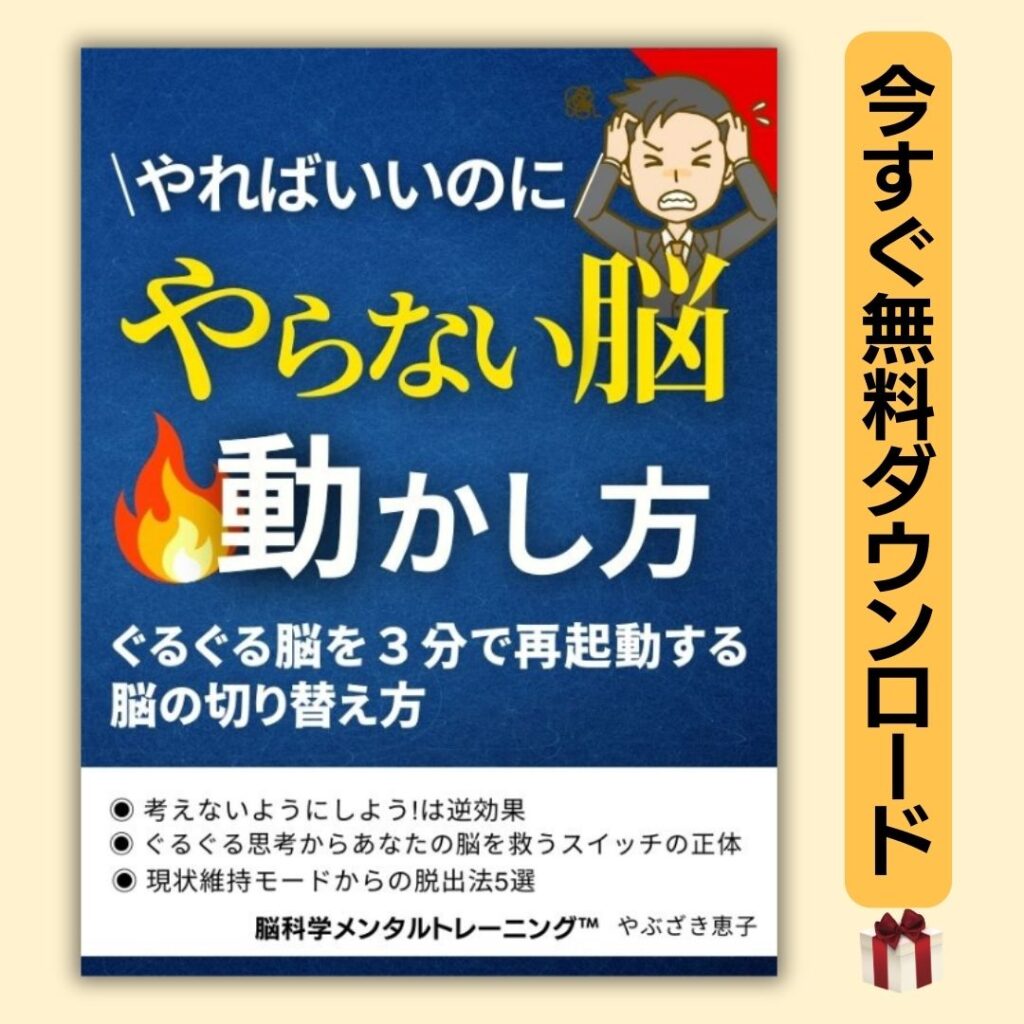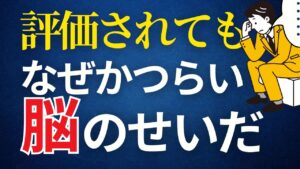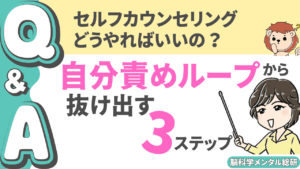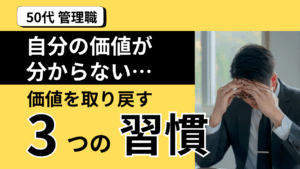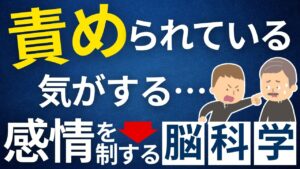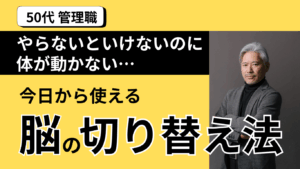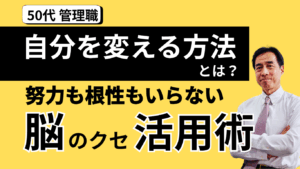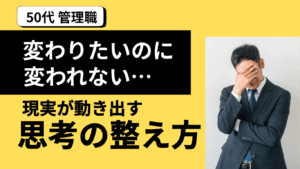人の気持ちが分かりすぎる。言われたことを全部受け取って辛い方へ。適度に距離を取り、冷静に対応できるようになる3ステップを紹介します!
【相談】敏感過ぎて、言われたことを全部受け取ってしまう
 Kさん/50代/中間管理職(会社員)/千葉県
Kさん/50代/中間管理職(会社員)/千葉県敏感すぎて
言われたことを全部受け取ってしまうんです。
人の気持ちが分かりすぎて…
上司から言われたことを真正面から受け止めてしまって
自分が悪いって思ってしまって辛くて…



相手との精神的な距離を置けるようになると
全部受け取ることがなくなり
余裕が生まれるので冷静に対応できるようになりますよ。
敏感過ぎても、言われたことを受け取らない方法



敏感過ぎても、言われたことを受け取らなくなるには
自分と相手との間に境界線を作りましょう!
相手との間に
適度な心の距離をつくることが大切です。
敏感過ぎて、相手の言葉全て受け取ってしまう人は
相手の言葉だけでなく
その感情や意図まで
深く考えすぎてしまう傾向があるんです。
特徴として
・「自分のせいかもしれない」と思い込みやすい
・必要以上に気を遣い、ストレスがたまりやすい
・相手の言葉に振り回され、気持ちが不安定になる
このせいで気持ちが揺さぶられ
ストレスがたまりやすくなります。
適度な距離感を持てるようになると
相手の言葉を自分のことのように
受け取らないようになります。
そうすると
心に余裕が生まれ
冷静に対応できるようになりますよ!
本記事では
敏感すぎても言われたことを受け取りすぎないための
具体的な方法を解説します。
ぜひ最後まで読んで
無駄に傷つかず、心穏やかに過ごして
日々の気持ちをラクにしていきましょう!
言われたことを全部受け取ってしまうのは、あなたが悪いわけではない!



敏感すぎるのは脳の特性によるもの。
自分を責めずに少しずつ対処していきましょう!
敏感すぎるって
すごく大変なことだと思います。
ちょっとした言葉でも深く考え込んでしまい
仕事でもプライベートでも気を遣いすぎて疲れて…
ときには
「自分が悪いのかもしれない」
「もっと鈍感になれたら楽なのに」
と思うこともあるかもしれません。
それは決して欠点ではなく
あなたの持っている
素晴らしい才能の一つなんです。
敏感すぎるというのは
相手の気持ちを察する力があるということ。
「相手の感情や空気を敏感に感じ取る力がある。」
これは
相手の気持ちを考えずに行動する人にはできない
とても貴重な能力です。
・人の気持ちに寄り添える
・周囲に気を配り、サポートできる
・細かな変化に気づける
このように
敏感な人だからこそできることがたくさんあります。
「 敏感すぎる=ダメなこと」
と思わなくて大丈夫なんです。
実は
敏感すぎるのは性格の問題ではなく
脳の働き方によるものなんです。
つまり
「脳の特性」によるものなんです。
人よりも情報をたくさん受け取り
深く処理する傾向があるため
ちょっとした言葉や表情の変化にも
敏感になりやすいのです。
敏感過ぎて、言われたことを全て受け取ってしまうのは
脳の特性であり
自分を責める必要はないんです。
自分を責めずに少しずつ対処していきましょう!
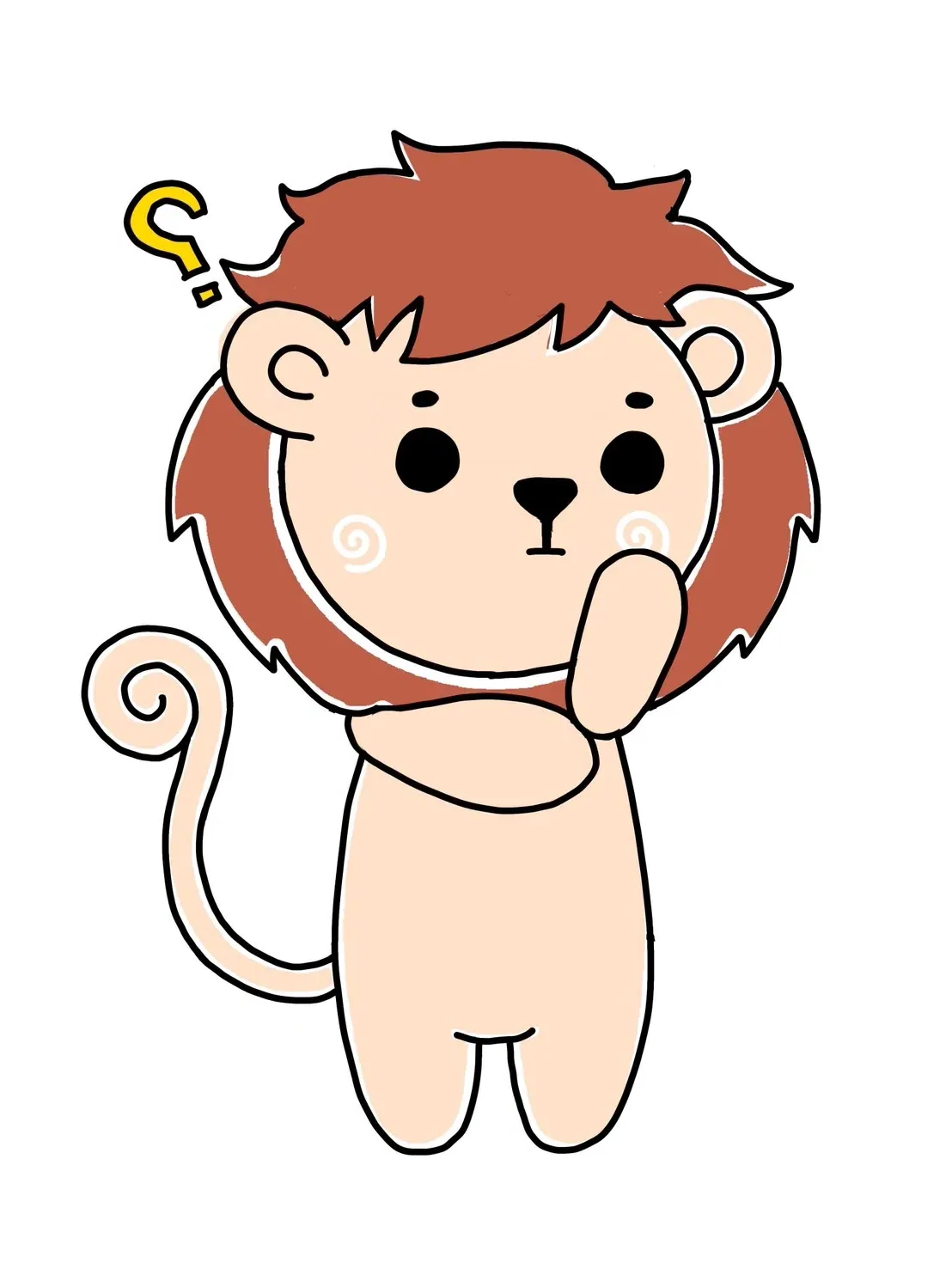
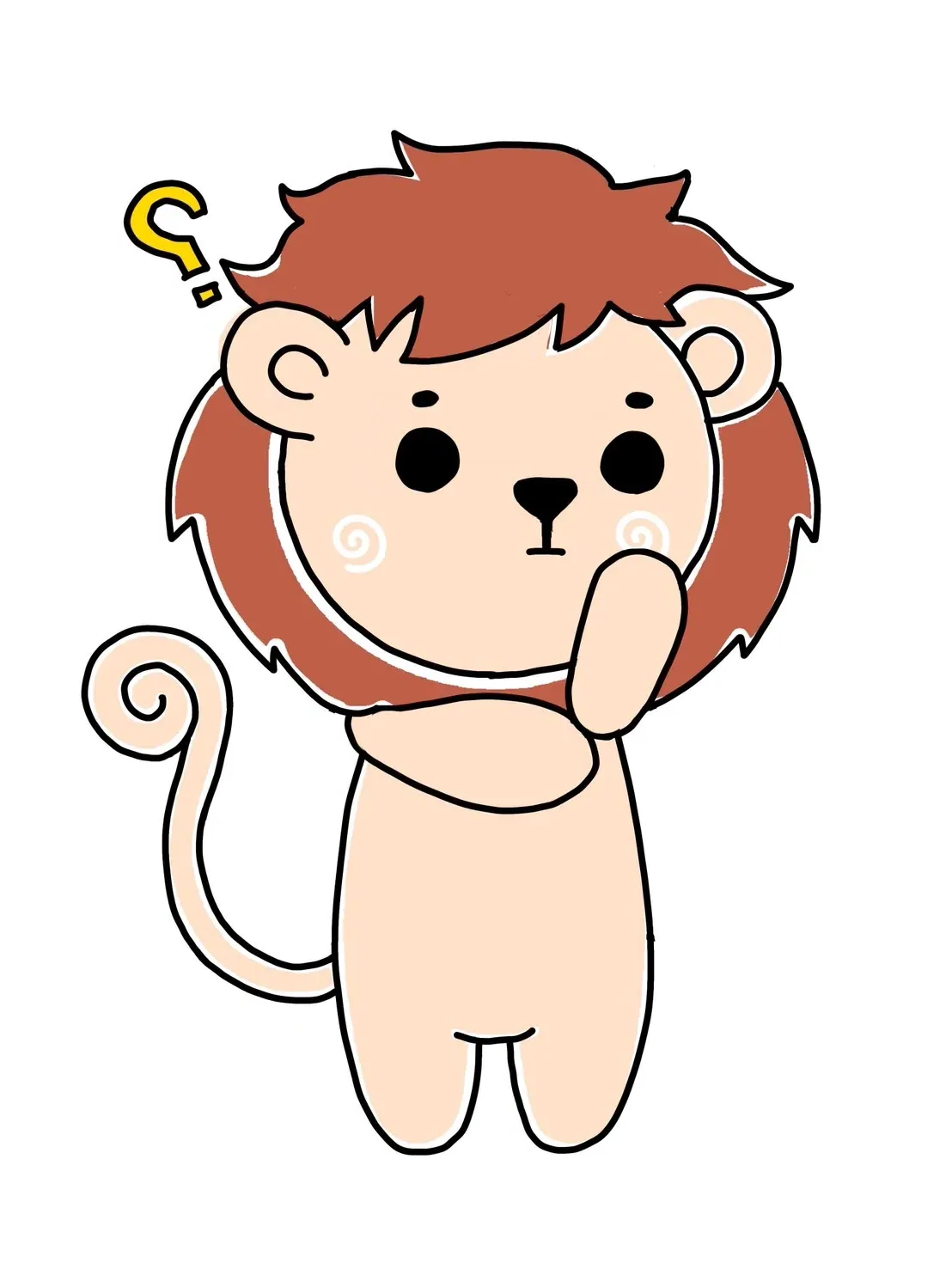
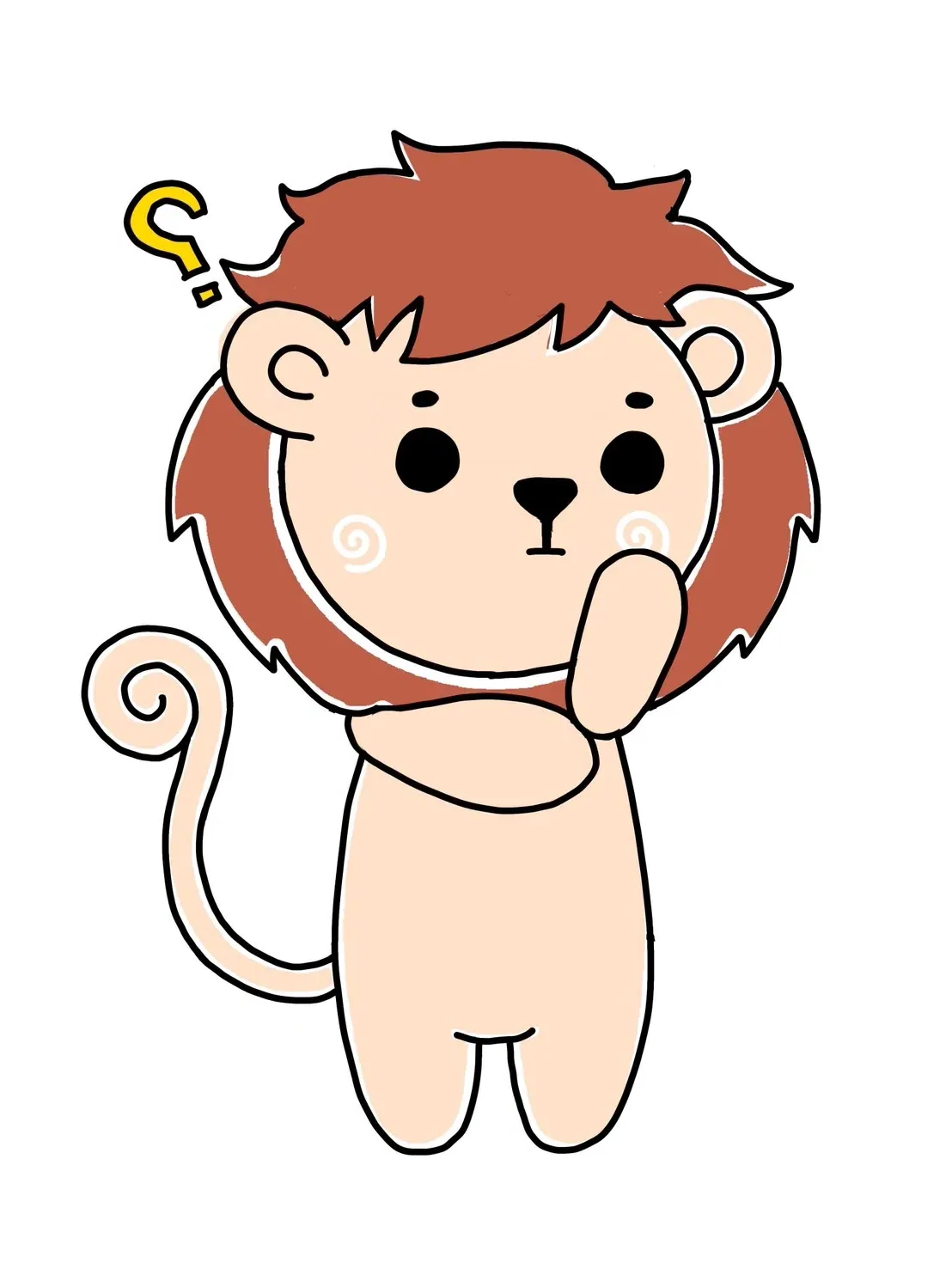
どうして言われたことをすべて受け取ってしまうの?
敏感すぎることには理由があるんです。
あなたがなぜ
言われたことをすべて受け取ってしまうのか
その原因を知ることで、
対処のヒントが見えてきます。
次の章では
その理由をわかりやすく解説していきますね。
敏感すぎて、言われたことを全部受け取ってしまう理由



どうして自分はこんなに気にしすぎてしまうんだろう?



実は、これは単なる性格の問題ではなく
脳の仕組みや環境の影響が関係しているんです
あなたが敏感に反応してしまう主な理由は
次のようなものがあります。
① ミラーニューロンの働き——共感しすぎてしまう脳の特性
ミラーニューロンとは
他人の表情や行動を自分のことのように
シミュレーションする神経細胞です。
この働きが強い人ほど
他人の感情に敏感になり
自分のことのように感じてしまう傾向があります。
例えば
・ 職場で誰かが怒られているのを見ただけで
自分が怒られているように感じる
・ 同僚の機嫌が悪いと、
「自分が何かしたのでは?」と不安になる
これは、共感力が高い証拠でもありますが
同時に「言われたことを全部受け取ってしまう原因」
にもなっています。
② 遺伝的な要因——共感しやすい気質は生まれつき?
脳の神経構造や感受性には
遺伝の影響も関係しています。
・共感性が高い遺伝的傾向を持つ人は
ミラーニューロンの働きが強くなる可能性がある
・「気にしすぎる」のは性格ではなく
「生まれつきの特性」の一部であることが多い
「敏感すぎる性格を直さなければ…」と
無理に変えようとする必要はありません。
自分の特性を理解し
上手に付き合っていくことが大切です。
③ 社会的な学習——環境が敏感さを強化している
人は成長する過程で
周囲の影響を受けながら
脳の働きを発達させていきます。
・ 幼少期から「人の気持ちを考えなさい」と言われ続けてきた
・ 職場で「空気を読むこと」が求められる環境にいる
・ 看護・教育・接客など、共感力が求められる仕事をしている
こうした環境では
脳が「他人の気持ちを察するスキル」を強化し
敏感さが増すのです。
つまり、敏感に反応してしまうのは
これまでの経験や環境によって
脳が「そうしたほうがいい」と
学習してきた結果でもあるのです。
④ 神経可塑性——繰り返しの経験が脳の働きを変える
脳には「神経可塑性(しんけいかそせい)」と
呼ばれる性質があり
繰り返し経験することで
神経回路が強化されます。
・日常的に他人の感情を気にする習慣がある
・共感を求められる環境で長年過ごしてきた
このような経験が続くと
敏感になりすぎる神経回路が強化され
より気にしすぎる傾向が強くなるのです。
逆に言えば
適度な距離を取る練習をすることで
「受け取りすぎるクセ」を和らげることも可能です。
⑤ ホルモンの影響——「愛情ホルモン」オキシトシン
オキシトシンは、人とのつながりを強め
共感力を高めるホルモンです。
このホルモンが多く分泌されると
他人の感情を
より強く感じ取りやすくなるとされています。
・親しい人との触れ合いで分泌が増える
・人の表情や感情を察する力を高める
敏感さは「ホルモンの影響」によっても
強化される可能性があるのです。
⑥ 心理的な傾向——敏感さを高める気質とは?
内向的な人や**HSP(Highly Sensitive Person:非常に敏感な人)**
の傾向を持つ人
感情の微細な変化に気づきやすく
他人の気持ちに深く共感しやすい
と言われています。
・ HSPの人は、周囲の感情に影響されやすい
他人の気分や雰囲気を敏感に察知し
それに引きずられやすい傾向があります。
・内向的な人は、言葉の意味や背景を深く考えすぎることがある
何気ない一言でも
「本当の意図は何だろう?」と考え込み
必要以上に気にしてしまうことがあります。
こうした心理的な特性は
「敏感すぎる」と感じる要因になることもありますが
決して悪いことではありません。
むしろ
「人の気持ちに寄り添う力がある」
「細やかな気配りができる」といった
大きな強みでもあります。
大切なのは、この敏感さを活かしながら
「必要以上に受け取りすぎない」ようにすることです。
敏感な人が言われたことを受け取らなくなる3ステップ
① 扁桃体の過活動を鎮める



扁桃体は「感情を司る脳の部位」で
ストレスがかかると過剰に反応するんです。
これを落ち着かせる
簡単な方法がありますよ!
✅感情を言語化する
まずは、自分が感じている「嫌なこと」は
どんな気持ちなのかを言語化します。
例えば
「上司から言われたことが辛い」
「 ストレスを感じる」とかです。
感情を言語化することで
自分の気持ちに気づき
気持ちを落ち着けることができるといわれています。
✅ おでこに手を当てながら深呼吸する


おでこに手を当てて、深呼吸をしながら
言語化した「嫌なこと」を考えます。
一般的には
嫌なことは考えない方がいいと言われますが
おでこに手を当てている時は考えても大丈夫!
おでこの内側の前頭前野というところは
感情をコントロールする働きをするので
感情が暴走するのを止めて
リラックスした状態に戻るからです。
おでこにあてた指先やおでこに
拍動を感じたら手を放して大丈夫です。
だいたい3分くらいで感じますが
慣れていない人は5分以上かかることもあるし
最初は感じない人もいるので
頃合いをみて手を離して大丈夫です。
✅ ストレス度合いを数値化する
次に最初に感じた嫌な気持ちの
ストレス度合いがどのくらいになったか
数値化してみましょう。
数値化することで
自分の気持ちを客観的に把握できます。
② 境界線を作るトレーニング
「相手の感情は相手のもの」
と意識するクセをつけましょう!
誰かに何か言われたとき
『これは相手の気持ちなんだ』とか
『相手はコントロールできないよね』とか
少し距離を置く練習をします。
✅ 水槽作戦
透明なアクリル板が自分と相手の間にあるイメージを持つ
自分と相手との間に
10センチくらいの透明なアクリル板があると
イメージしてみましょう。
相手は、もしかして
怒っているかしれないけど
それは
水族館の分厚いアクリル板の向こう側の話!
最初は難しいかもしれませんが
慣れてくると自分の心にゆとりが生まれますよ。
✅ ビッグハート🩷
大きいハートを自分の周りに描くように
両腕を動かします。
動かす時のポイントは
・動くときは息を吐く
・止まった時に息を一気に吸う
・遠くに遠くに広がるイメージ
両腕を動かしてハートを描くと
境界線がイメージでき
心の距離を意識しやすくなりますよ!
③ 脳のバランスを整える
✅質の良い睡眠をしっかりとる
「敏感さ」を和らげるためには
十分な睡眠が欠かせません。
睡眠不足の状態では、
脳の情報処理がうまくいかず
「普段なら気にしないこと」にも
過剰に反応してしまいやすくなるからです。
・睡眠時間を確保する(理想は6〜8時間)
・寝る前にスマホを見ない(ブルーライトが脳を覚醒させる)
・カフェインの摂取を控える(夕方以降のコーヒーやお茶は控える)
睡眠がしっかりとれていると
脳が落ち着き
「言われたことを全部受け取ってしまう」クセが
和らぎやすくなります。
✅ 脳を整えるエクササイズをする
偏桃体の過剰な興奮を鎮めて
前頭前野を活性させて脳を整えましょう!
わくわくステップ
1. その場で足踏みします
2. 右手で左の膝をタッチします
3. 左手で右の膝をタッチします
これを1分続けるだけ!
体を動かすことで血流が増え
左右の手足を交差させて動かすことで
脳のバランスが取れるようになります。
こうした習慣を取り入れることで
「言われたことを全部受け取ってしまう」クセが
少しずつ和らぎ
気持ちに余裕が生まれるようになります。
無理せず、できることから試してみましょう!
まとめ:敏感な人が言われたことを受け取らずに冷静さを保つ方法
敏感すぎて言われたことを全部受け取ってしまうのは
あなたが悪いわけではありません。
それは、脳の特性やこれまでの環境
心理的な傾向によるものだからです。
すべての言葉を真に受け続けると
心が疲れ切ってしまいますよね。
だからこそ
適度に距離を取り
冷静に対応できるようになる方法を
身につけることが大切です。
敏感さとうまく付き合うための3ステップ
① 扁桃体の過活動を鎮める
・気持ちを言語化・数値化し
「今、自分は何を感じているのか?」を客観視する
・おでこに手を当てて深呼吸し、ストレスを和らげる
② 境界線を作る練習をする
・これは相手の感情、自分のものではない」と意識する
・水槽作戦(透明なアクリル板をイメージ)で、心の距離を保つ
・ビッグハート🩷(大きなハートを描く動き)で、 心の距離の感覚をつかむ
③ 脳のバランスを整える
・睡眠の質を向上させ、脳の疲れをとる
・わくわくステップ(足踏み+膝タッチ)で、脳を活性化する
「敏感さ」はあなたの強みになります。
敏感な気質は、「弱点」ではなく
「人の気持ちに寄り添う力」でもあります。
その力をうまくコントロールしないと
必要以上に傷ついたり、
疲れたりしてしまいます。
今回紹介した方法を取り入れて
言われたことを受け取りすぎない習慣を
少しずつ身につけていきましょう。
焦らず、自分のペースで取り組んで大丈夫ですよ!
この時に気を付けたいのが
脳の中が非常事態になってしまっている。
つまり、火事の火が消されてないような
状態になっているということ。
そのような状態では
変化の表れ方もかわってきます。
まずは、脳を整えるエクササイズ基本編で
脳を整えておきましょう!!
これができない状態で脳のバランスを取ろうとしても
「グルグル思考」の時間が増えるだけです。
ぐるぐる思考を止めるためには
「もう、悩まない!読むお薬」を読んでみてくださいね!