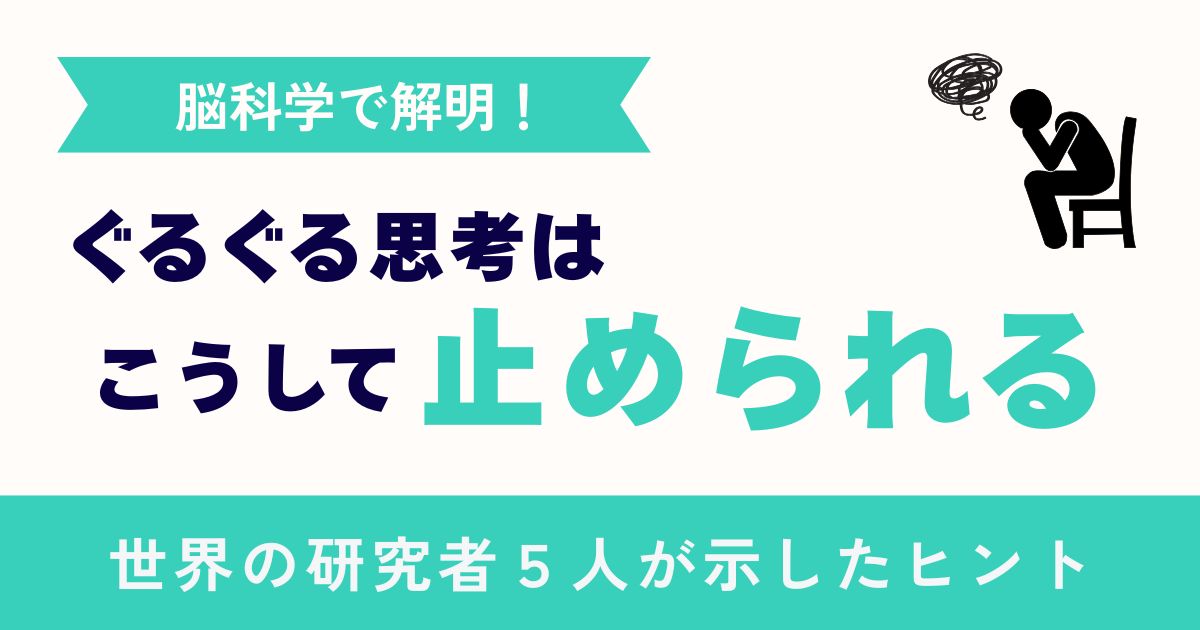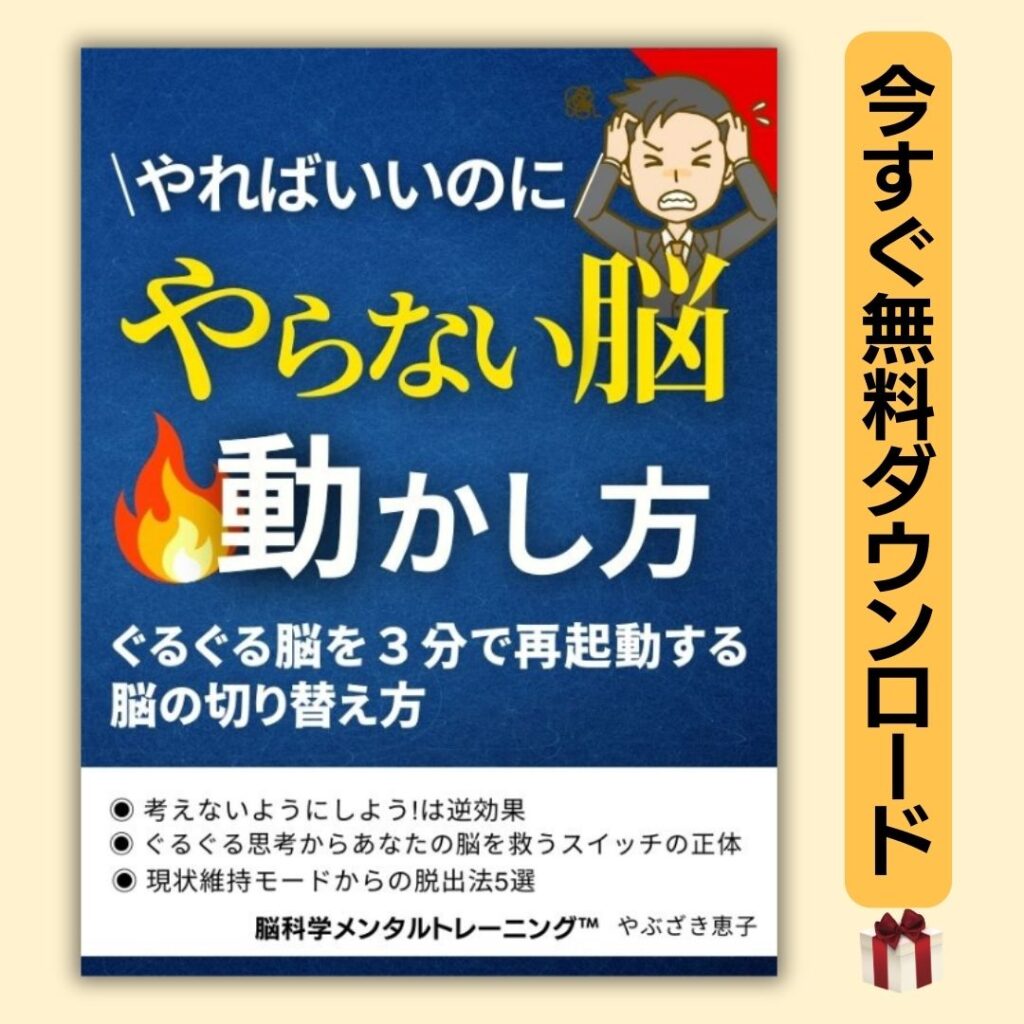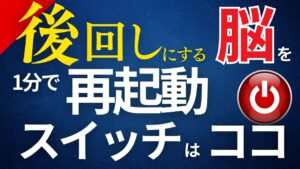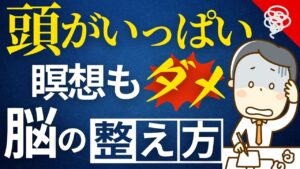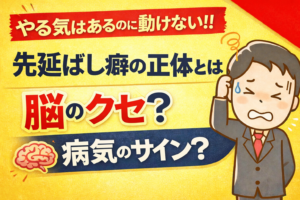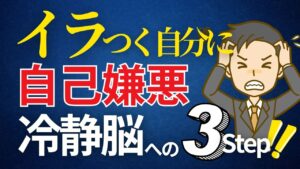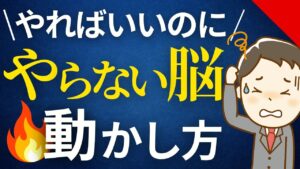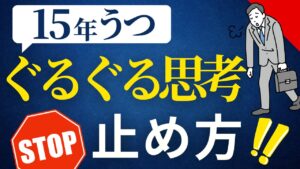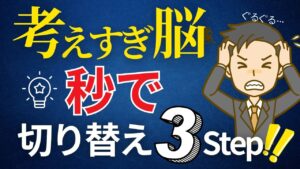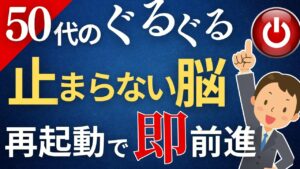脳科学メンタル総研いのかおる
脳科学メンタル総研いのかおる昨日のプレゼンのこと、また頭の中でぐるぐる考えちゃってる?



うん…。
自分が何を言ったか、上司の表情とか…
考え始めたら止まらないんだよね。



それ、“脳のクセ”が原因かもしれないよ!
実は世界の研究者たちも、
その「ぐるぐる思考」について研究しているの。
紹介するね。
この記事のハイライト
・ぐるぐる思考の正体は“脳の働きすぎ”だった!?
考えすぎてしまうのは、性格のせいでも、意志の弱さでもありません。脳が“自分を守ろうと頑張っている証拠”だったのです。
・世界の研究者5人が示す「止め方」と「考え方」
反芻思考・セルフトーク・メタ認知・ポジティブ定着・マインドフルネスといった各分野の専門家が提案する“やさしく脳を整える視点”を紹介します。
ぐるぐる思考は「あなたの脳が正常に働いている証拠」
脳はネガティブに偏る仕組みがある



「昨日のあの一言、やっぱり余計だったかな…」
「なんであんな態度を取られたんだろう?」
寝る前やふとした時に、1日の出来事が“ネガティブ目線”で頭の中をぐるぐる回り始めてしまう…そんな経験はありませんか?
安心してくださいね!
その反応、あなたの脳がちゃんと“仕事をしている”証拠なんですよ。
私たちの脳には、「ネガティブな情報」を優先的に扱うクセがあります。
これは、進化の過程で生まれた“生き延びるためのしくみ”です。
たとえば──
太古の時代、危険(=ネガティブ)に敏感な人ほど命が助かりやすかったんです。
狩りをして生活をしていた時代を想像していただくとイメージしやすいと思います!いつ何時、何かに襲われるかもしれない!あるいは自分が獲物を見つけて襲いかかるのか?分からないですよね。
だから脳は「危なかったこと」「失敗したこと」を強く記憶し、再発防止のために繰り返し思い出すようになっています。
つまり、“ネガティブに偏る”のは脳の自然な働き。
それは、あなたに問題があるからではなく、あなたの脳が「正常に働いている」からこそ起こる反応なのです。
ぐるぐるするのは“考えすぎ”ではなく“思考のクセ”



なぜ私たちはそこから抜け出せず、
何度も何度も同じことを考えてしまうのでしょうか?
その原因のひとつが、反芻思考(はんすうしこう)と呼ばれる
脳のパターンです。
反芻とは、私たちの脳が過去の出来事や言葉を「リピート再生」のように何度も流れ続ける状態です。
これは、危機回避のための“思考のクセ”として脳に根づいてしまうことがあります。
たとえば──
- 1つのミスを夜まで引きずる
- 相手の何気ないひと言がずっと気になる
- 「あのときこうしていれば」と過去をぐるぐる思い続ける
そんなとき、私たちは「自分は考えすぎだ」と思いがちなのですが、
実際には、脳が自動的に“反復モード=ぐるぐる思考”に入っているだけなのです。
世界の研究者5人が教える「ぐるぐる思考の止め方」



ぐるぐる思考を止めたい…
そう頭では分かっていても、
「どうやって止めればいいの?」
「いったい何をすればいいの?」
それが分からないから辛いし、苦しいですよね。私もその一人でした。
ここからは、ぐるぐる思考に向き合ってきた世界の研究者たちをご紹介します。
研究者それぞれに異なる角度から「ぐるぐる思考」のしくみと止め方のヒントを教えてくれています。
ご自身と照らし合わせながら読み進めてみてくださいね!
①スーザン・ノーレン=ホークセマ(アメリカ)
ぐるぐる思考(反芻思考)の“感情ループ”を断ち切る方法
アメリカの心理学者スーザン・ノーレン=ホークセマは「反芻思考(rummation)」という概念を広め、
特に女性のうつ傾向に深く関わる“思考のループ”に注目しました。
ぐるぐる考えすぎてしまうとき、感情も同じように“ぐるぐる”していませんか?
彼女は「気づくこと」がループ脱出の第一歩だと提唱しています。
「あッ!今、私またぐるぐる考え込んでるな」と気づけただけで、感情と思考のループに“すき間”が生まれるんです。
感情の“取扱い方”のアプローチの深さ
スーザン・ノーレン=ホークセマの理論では、ぐるぐる思考に気づいたあと「注意をそらす」「気分転換」「行動へ移す」といったことを推奨していますが、その方法はやや抽象的です。
一方で脳科学メンタルトレーニングでは、「気づいたあと、何が起こっているか(=脳がどう反応しているか)」を理解することで、“自責”や“意味づけぐるぐる”をストップさせやすくしています。
②イーサン・クロス(アメリカ)
セルフトークを“俯瞰”する方法
次にご紹介するのは、ミシガン大学のイーサン・クロスは、
著書『チャター』で、私たちの中にある「内なる声」との向き合い方について、とても深く掘りさげています。
彼が提唱しているのは、自分のことを「あなた」と呼んでみるという方法!
“自分を少し外から見る”ことで感情の整理がうまくいくという「距離を取るセルフトーク(distanced self-talk)」の一種です。
たとえば、「私はなんであんなこと言っちゃったんだろう…」というセルフトークを、
「(自分の名前)さん、それを言ったとき、どんな気持ちだったの?」という質問に変えて自分の気持ちを“他人として”問い直すといったイメージです。
手法の軸が言葉 or 脳・体感
イーサン・クロスは言葉(セルフトーク)を使って、自分を他者化するアプローチする方法を説いています。
「自分=私」を「あなた・名前」で語ることで、前頭前野を活性化し感情を落ち着ける戦略です。
一方脳科学メンタルトレーニングでは、脳の反応・体感を使って「安心の神経システムをONにする」アプローチします!思考ではなく“脳と体”に働きかけて安全・安心の回路をつなぎ直すのが特徴です。
③エイドリアン・ウェルズ(イギリス)
メタ認知で“思考のクセ”に気づく方法
3人目は、メタ認知療法(MCT)を提唱したイギリスのエイドリアン・ウェルズさん。
彼の考え方は、「考えすぎを止める」というよりも、「考えとの関わり方を変える」という考え方です。
たとえば、「ぐるぐると考えている内容(考え)を重要だと思いすぎるクセ」や、「この考えを止めないと、何か悪いことが起こるかも…」という思考への思い込みに注目をしました。
では、思い込みモードに入ってしまった時どうするのか?というと
「この考え(ぐるぐる考えていること)、今ここで必要?」とやさしく問いかけることで、
考えること自体を悪者にするのではなく、
「それ、いま扱わなくても大丈夫だよ」と教えてあげる感覚でぐるぐる思考にアプローチしていきます。
「思考」か「脳」か!アプローチのスタート地点が違う
メタ認知療法では、“思考”との関わり方を変える → 「この考えは脅威ではない」と再認識し「思考の受け止め方」にアプローチします。
脳科学メンタルトレーニングでは、“脳の反応”そのものを落ち着かせる → 安心回路をつなぎ直すことで、ぐるぐる思考に巻き込まれなくなるというアプローチ方法をしていきます。
④リック・ハンソン(アメリカ)
ポジティブな記憶を“脳に定着”させる方法
4人目は、神経心理学者のリック・ハンソンさん。
彼は「脳はネガティブにはすぐ反応するけれど、ポジティブは流れてしまいやすい」と提唱しています。
じゃあ、どうすればいいのか?
彼のアプローチはとてもシンプルなんです!
「うれしかったこと、感謝されたことを、3秒間じっくり味わう」
たったこれだけで、脳に“ポジティブな回路”が作られていくそうです。



実は私も朝起きた時、夜寝る前に「よかったこと」を思い出し、
味わう習慣を続けています。
私の感覚ですが、毎朝その日1日がポジティブにスタートできる感じがしています!
「ぐるぐる思考からの回復」に強いかどうか
ハンソンの理論では、感情や気持ちが落ち着いている状態の人が「日常の幸福感や回復力(レジリエンス)」を高めたり、定着させていくという考え方です。
一方で脳科学メンタルトレーニングでは、脳・神経・ホルモンにアプローチしながら“今まさにぐるぐるしている”状態からのリセット&切り替えに即効性が高いメソッドです!
⑤マーク・ウィリアムズ(イギリス)
“今ここ(今の現状)”に戻るマインドフルネス的思考リセット法
最後にご紹介するのは、マインドフルネス認知療法の共同開発者マーク・ウィリアムズさん。
彼は「過去や未来に引っ張られがちな脳を“今ここ”に戻す力」の大切さを説いています。
人はストレスや不安に直面すると、「自動思考(ネガティブなクセ)」に巻き込まれていく傾向があります。
ぐるぐるしているとき、頭の中は「さっきのこと」や「これからのこと」でいっぱい…ですよね!
そんなときは、まず呼吸に意識を戻すだけでOK!と説いているんです。
「今、自分は息をしてる」
「今、足が床に触れて冷んやりするな」
こんなシンプルな感覚のひとつひとつが、脳の再起動スイッチになるそうです。
頭の中で考えるのをやめて、
「今この瞬間の呼吸・音・身体感覚に意識を戻す」という練習を通じて、ぐるぐる思考のループから抜け出します。
「ぐるぐる思考に巻き込まれる理由」の見方とアプローチの深さと広さ
ウィリアムズは、ぐるぐる思考に巻き込まれるのは「自動思考=クセ」に気づけていないからと説き、解決法としては意識的に“気づく”ことで思考から距離を取ると説いています。
一方、脳科学メンタルトレーニングでは、ぐるぐる思考に巻き込まれている状態を「脳が今とても危険だ!と判断し、防衛モードに入っている」と捉え、解決法として「脳が安心」と判断できる環境・刺激を与える方法でアプローチをしています。
あなたに合った「ぐるぐる思考対策」はどれ?



無理に考えを止めようとしてもうまくいかない…
そんな経験はありませんか?
私は一晩中ぐるぐる考えて朝をむかえる人でした!
実は、ぐるぐる思考には“人それぞれのクセ”があるんです。
「私はどのタイプ…?」と思った方は、3つの質問に答えて思考タイプをチェックしてみてくださいね。
ぐるぐる思考と、優しく付き合っていこう
ぐるぐる思考に悩んでしまうのは、あなたが弱いからではありません。
それは「脳がちゃんと働いている証拠」であり、「あなたを守ろう」としている自然な反応なのです。
だけれど、そのぐるぐる思考がつらく感じるときは──
「このクセ(ぐるぐる思考)は、少しずつ変えていくことができる」と思い出してみてくださいね。
この記事でご紹介した世界の研究者たちは、
ぐるぐる思考に対して“さまざまな出口”を示してくれました。
それはつまり、“あなたにも合うぐるぐる思考の止め方”がきっとあるということ。
そして、私が実践している脳科学メンタルトレーニングでは、
「今まさにぐるぐる思考でつらく、苦しい」と感じているその瞬間から働きかけられる
安心・体感・脳の回路に基づいたアプローチで、自分自身をサポートをしています。
凄く小さな一歩でも、それは確かな変化につながっていきますよ。
この記事を読んでくださったあなたもちゃんと変われる力を持っています。
そのことを、どうか忘れないでくださいね〜!