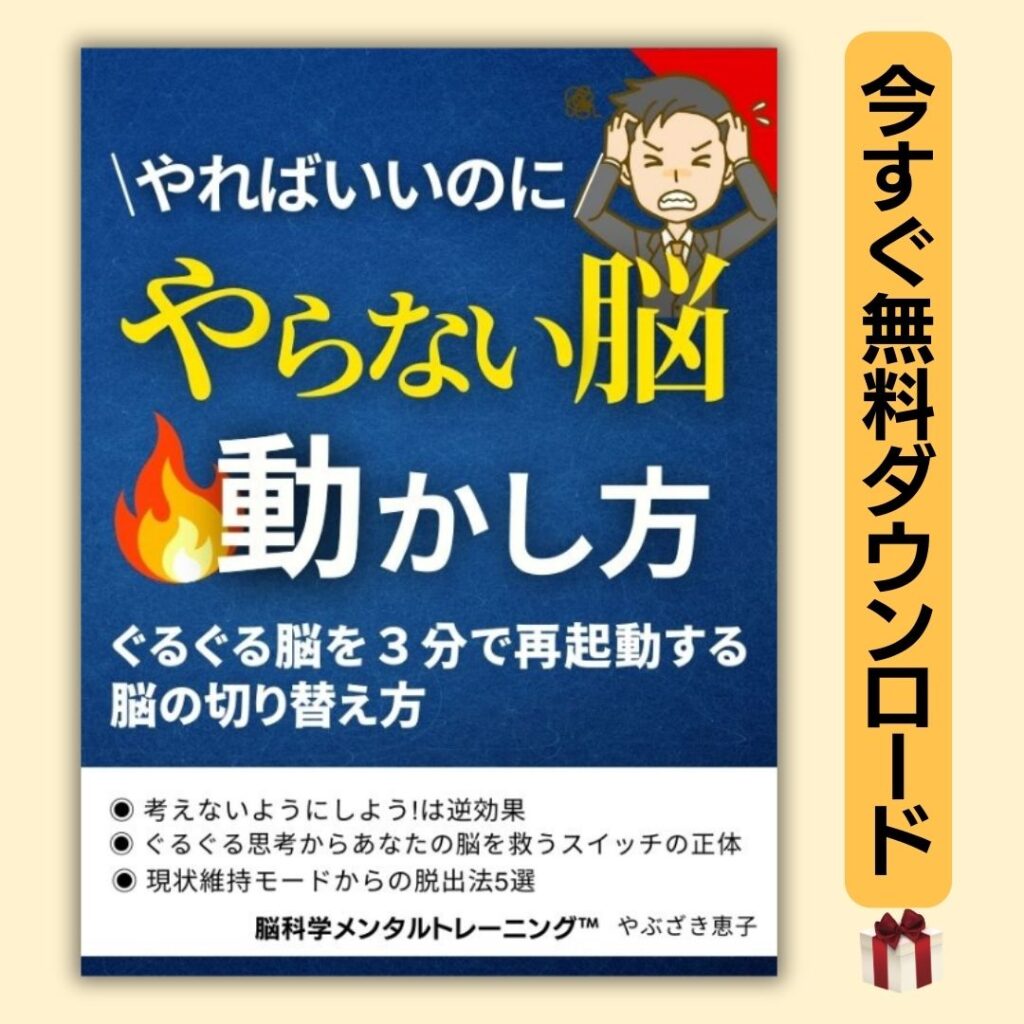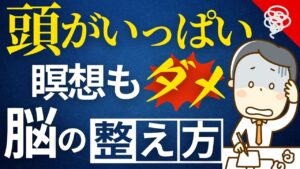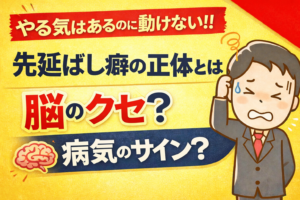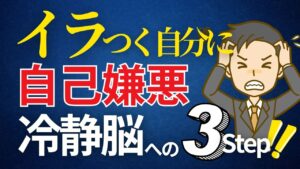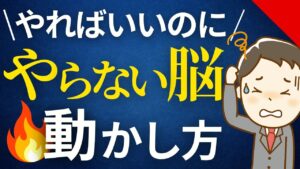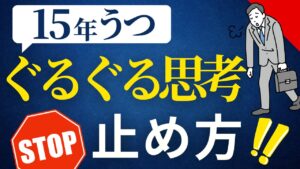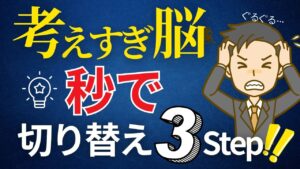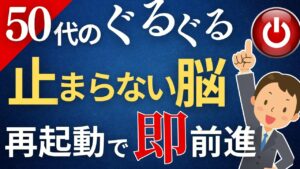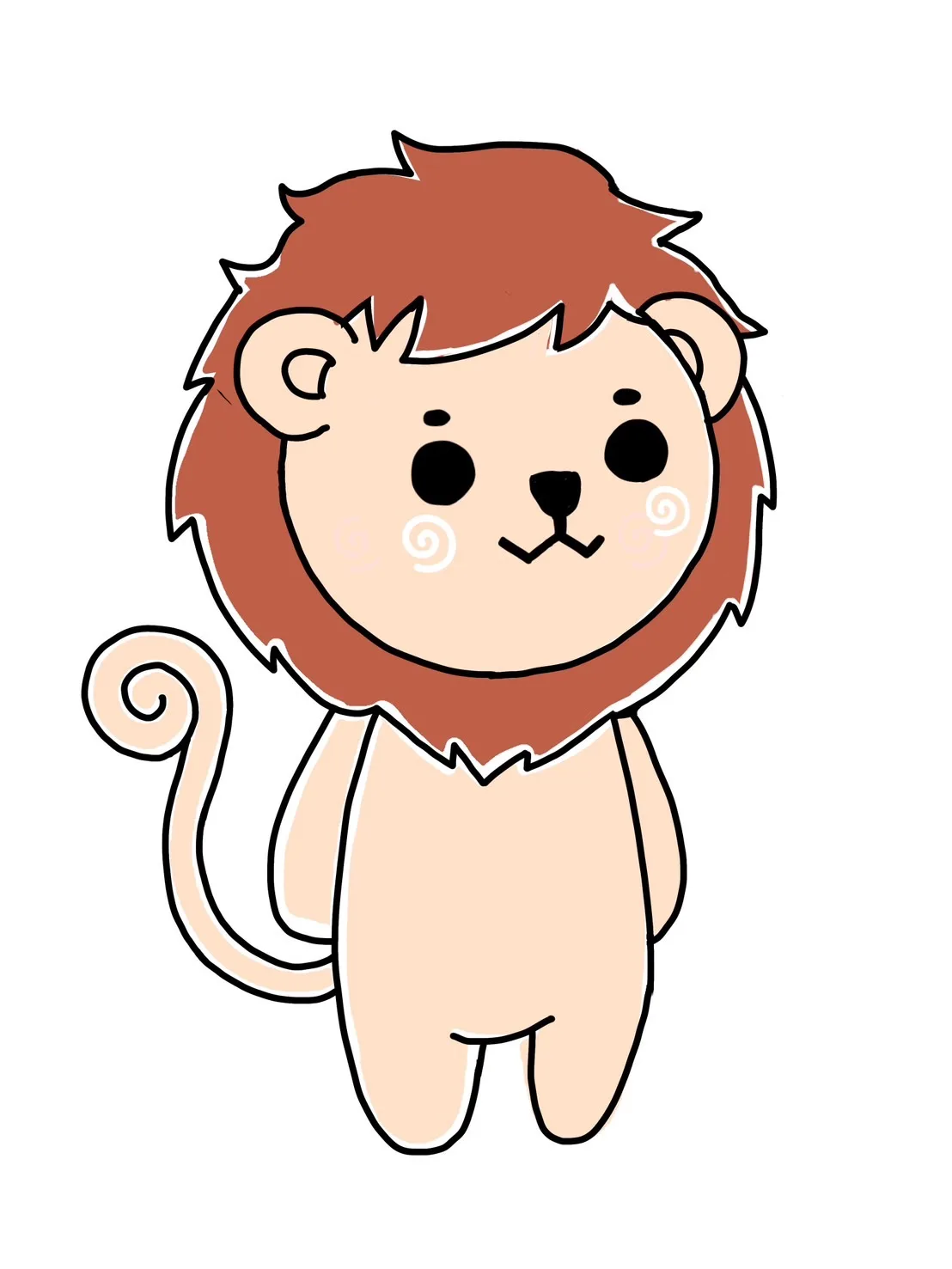 メンタくん
メンタくん“緊急なことより重要なことを優先しろ”
って何度も言われるけど、
つい目の前の雑務に流されちゃうんだよね…



そうそう、“頭ではわかってるのに、行動できない”って人に多いんですよ。今日はその原因と、すぐできる対処法をお伝えしますね!
この記事のハイライト
・「やる気はあるのに行動できない」は脳の仕組みのせい
・「かっこいいと思える行動」を朝に1つ書くと行動が変わる
・自分の先延ばしタイプを知ると、自己嫌悪ループから抜け出せる
・脳は3分でリセットできる。“再起動”は誰にでも可能
セミナーでも尊敬する経営者も、みんなこう言う
そう耳タコになるほど言われたこと、ありませんか?
実際に、ある会社役員のMさん(52歳)もこう話してくれました。
「分かってるんです。みんな大事なことからやれって言いますから。
だけど、メール返信や経費処理みたいな緊急の雑務に追われて、
気がついたら一日が終わってるんです…。
自己嫌悪ですよ。」
やる気はあるのに、なぜ行動できない?
その答えは「脳」にあります。
やるべきことが“習慣化”されていない状態では、
脳は「ラクで慣れたこと=緊急の雑務」に逃げがちです。
つまり「重要なこと」は、放っておくと自然には手をつけにくい。
毎朝3分|「これをやってる自分ってかっこいい」を書くだけ
そこでオススメしているのが、この習慣。



これをやってる自分って、かっこいい
と思えることをノートに1つだけ書き出す。
たったそれだけ。
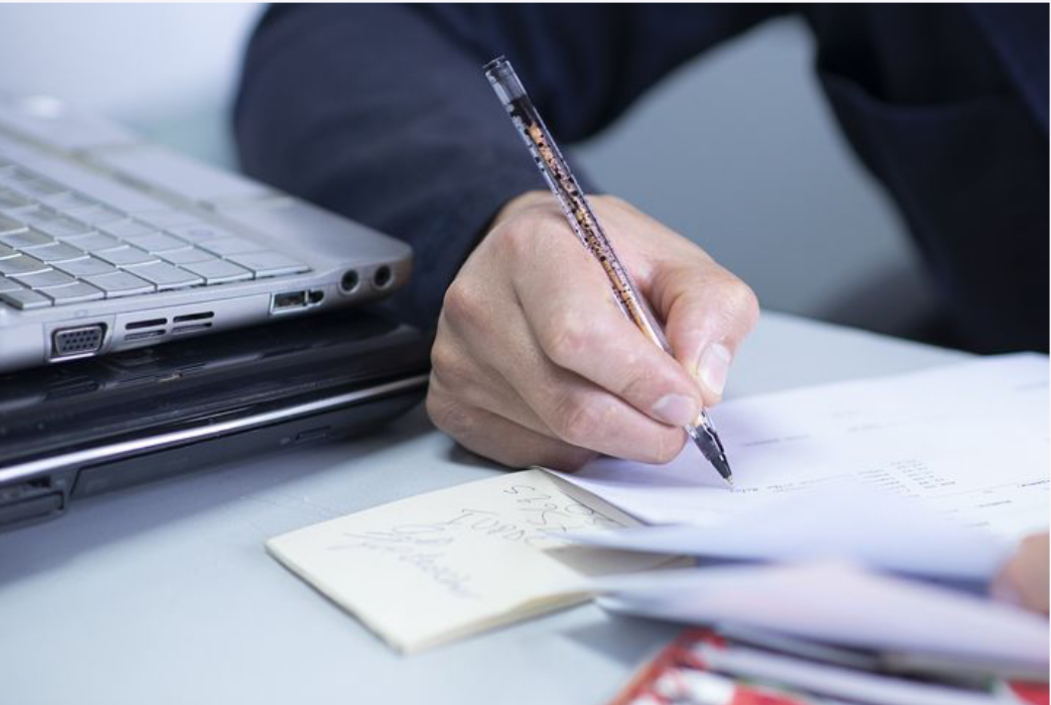
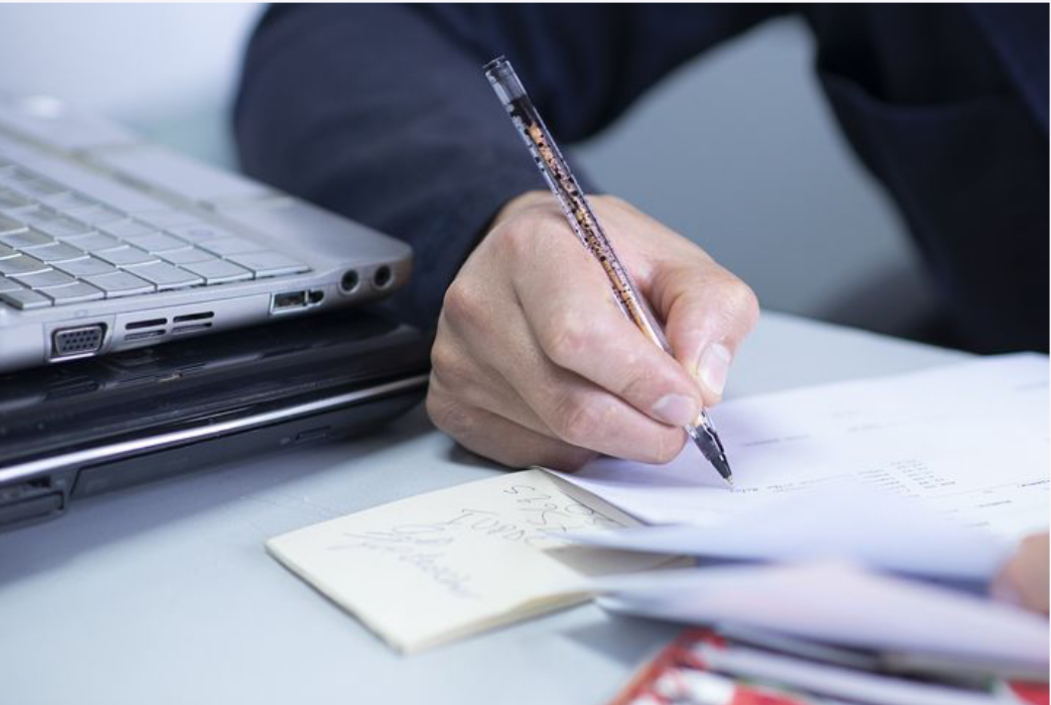
これは『緊急なことより重要なことを優先しろ』という“耳タコの言葉を行動に変えるスイッチ”になります。
Mさんもこの習慣で変わりました。
メール返信や経費処理という目の前の作業にばかりしていた日々から
そんな“未来につながる行動”が自然とできるようになりました。
「誰かみたいに振る舞いたい」もOK!
Mさんの他にも…
・56歳のSさん:「中井貴一さんみたいに、落ち着いて話せる男に」
・51歳のHさん:「田坂広志さんみたいに、自然に触れる時間を持つ」
そんな“かっこいい理想像”を描くだけでも、行動の軸がブレなくなっていきます。
大事なのは「やるべきこと」じゃなく「かっこいいかどうか」
「かっこいい自分」を思い描いて、それを言葉にして記録しておき、1日を過ごすと
「今日は、未来につながる一歩を進めた」
そんな満足感で1日を終える自分に、変わっていけるんです。
大事なのは「やるべきこと」
ではなく、「かっこいいか、カッコ悪いか」。
あなたも、まずは明日の朝、
ノートに
「こんな自分はかっこいいよな」
と、思えることを書いてみてください。
さらに、
自分の“先延ばしのタイプ”を把握すると、
この一歩が加速します。
なぜかというと
自分の傾向を知らないで、
なんとかしようとすると
余計にぐるぐる考えてしまって
時間とエネルギーを消耗して
やる気はあるのに動けない状態から
抜け出せないからです。
自分の“先延ばしのタイプ”を知ると、もっと加速する!
なぜかというと…
自分の傾向を知らないと、ぐるぐる悩んでエネルギーを浪費してしまうから。
自分の先延ばしのクセ、あなたは知っていますか?
🎁無料でチェック!1分でわかる【先延ばしタイプ診断】
\頭ではわかってるのに行動できない人、必見!/
👉 先延ばしタイプ診断はこちら(1分でチェック)
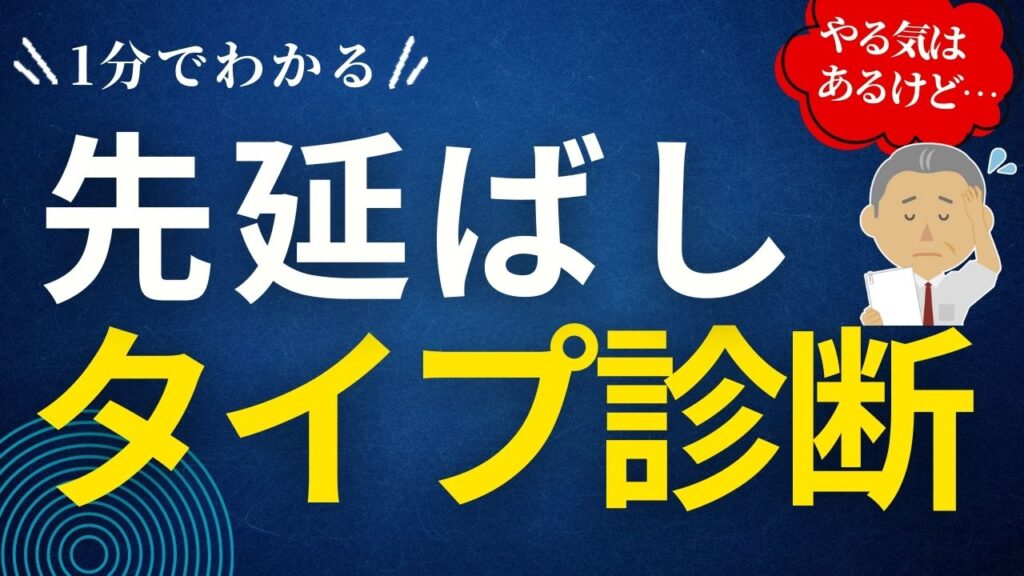
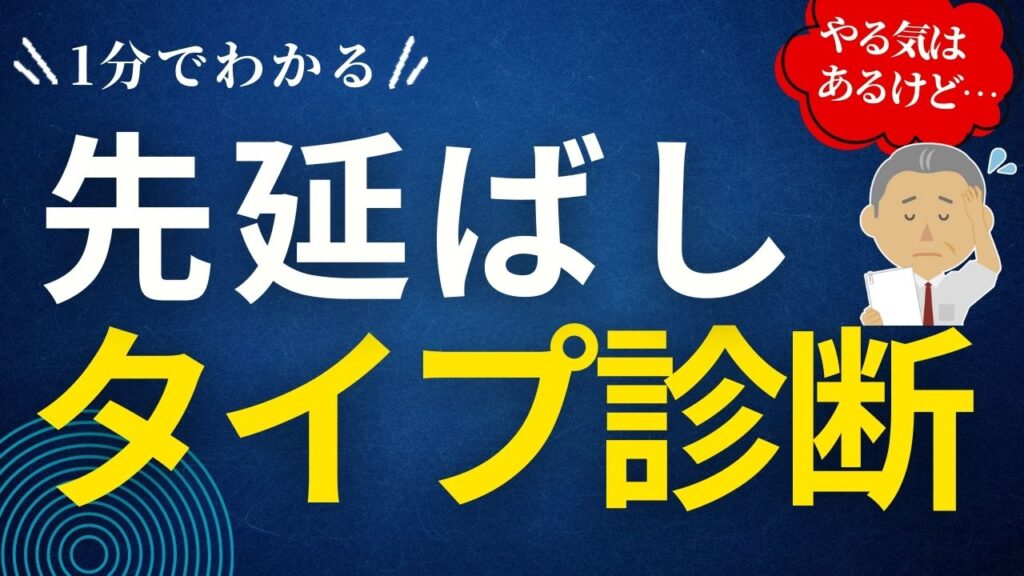
私自身も「やる気はあるのに動けなかった」
かつての私は「中途半端」「飽きっぽい」「気分で動く」タイプでした。
けれど今では、2,500件以上のセッションを行い、
“やる気はあるのに動けない人”をサポートする側になっています。
実際にこんな変化が起きています
💬 Mさん(52歳・会社役員)
「もうダメだ…」と思っていたけれど、
3ヶ月で行動力が戻り、売上もV字回復!
💬 Sさん(営業部長)
「自分はできない」とぐるぐる考えていた日々から脱出。
部下や取引先に「男前ですね」と言われるように。
“また今度ボタン”を脳から外す方法
やる気はあるのに動けないのは、
脳が「また今度でいいや」と勝手に判断しているだけ。
脳科学メンタルメソッドでは、
たった3分でこのクセをリセットできる再起動スキルを伝えています。
最後に。私からあなたへ伝えたいこと
「このままで終わるのか…?」
そう感じているあなたへ。
人生はここから、変えられます。
もう一度、「まだまだやれる」と思える毎日を。
次は、あなたの番です。
よくある質問FAQ
- 自分で考えて行動できない人の特徴は?
-
脳科学的に見ると、「自分で考えて行動できない人」は以下のような状態になっています。
1.思考過多(反芻脳・ぐるぐる脳):
同じことをグルグル考え続け、脳が“処理中”から抜け出せない。2.決断回避傾向:
不安や失敗の恐れが強く、前頭前野のブレーキ機能がうまく働いていない。3.過去ベースで考えている:
過去のミスや他人との比較から「どうせ自分は…」と判断を止めるクセがある。4.他者評価モードに偏っている:
自分軸より「どう思われるか」を先に考えすぎて、行動がストップする。脳科学メンタルトレーニングでは、こうした無意識の脳の反応パターンを見直し、
「自分で選び、動く」ための脳の回路を再構築していきます。 - 考えてばかりで行動できないのはなぜですか?
-
それは、“脳の中が混線している状態”だからです。
- あれもやらなきゃ、これも気になる…と同時に複数の判断をしようとして脳がフリーズ
- 感情のセンサー(扁桃体)が敏感で「やらない理由」ばかりが頭に浮かびやすい
- 過去の失敗を何度も再生する「記憶のループ」が止まらない
その結果、
思考はしているのに、脳は「決断しない」という選択を繰り返してしまうのです。この状態から抜け出すには、「思考から行動への橋渡し」をするワークが必要です。
例:
・ノートに書く(思考を可視化して脳を整理)
・「やること」より「やったらかっこいいこと」を優先順位にする
・3分だけ行動してみる(行動起点でドーパミンを出す)脳は“行動後”に変化する生き物です。
だからこそ、小さな行動が最強の思考整理になります。 - 頭でっかちの原因は?
-
「頭でっかち」と言われる状態の多くは、
思考と感情が“未処理のまま”脳に滞留していることが原因です。以下のような特徴が見られます:
- 本や情報はたくさん知っているけれど、現場で活かせない
- 「完璧なタイミング」を待って動けない
- 知ってるのに、やらない(=脳が“安心”だけを選びたがる)
これは脳が「知らない=不安」だった時代の防衛本能の名残です。
けれども現代では、情報を入れるだけでは人生は動きません。
脳科学メンタルトレーニングでは、知識を「行動に変える脳の使い方」にフォーカスします。
- 行動前提の知識に絞る
- 情報を“自分の状況に当てはめる”トレーニングをする
- あえて完璧じゃない状態で動く練習をする
こうすることで、頭でっかちだった脳が「実践型の脳」へと変わり始めます。