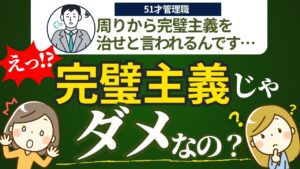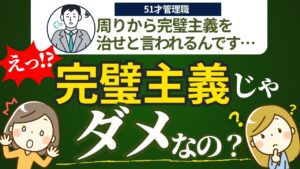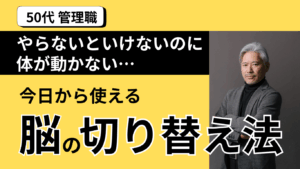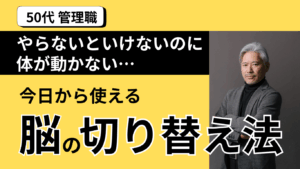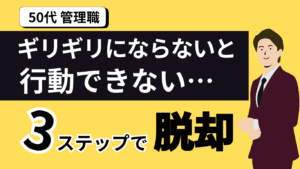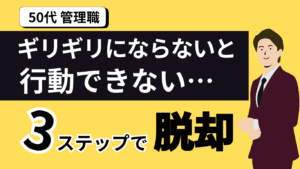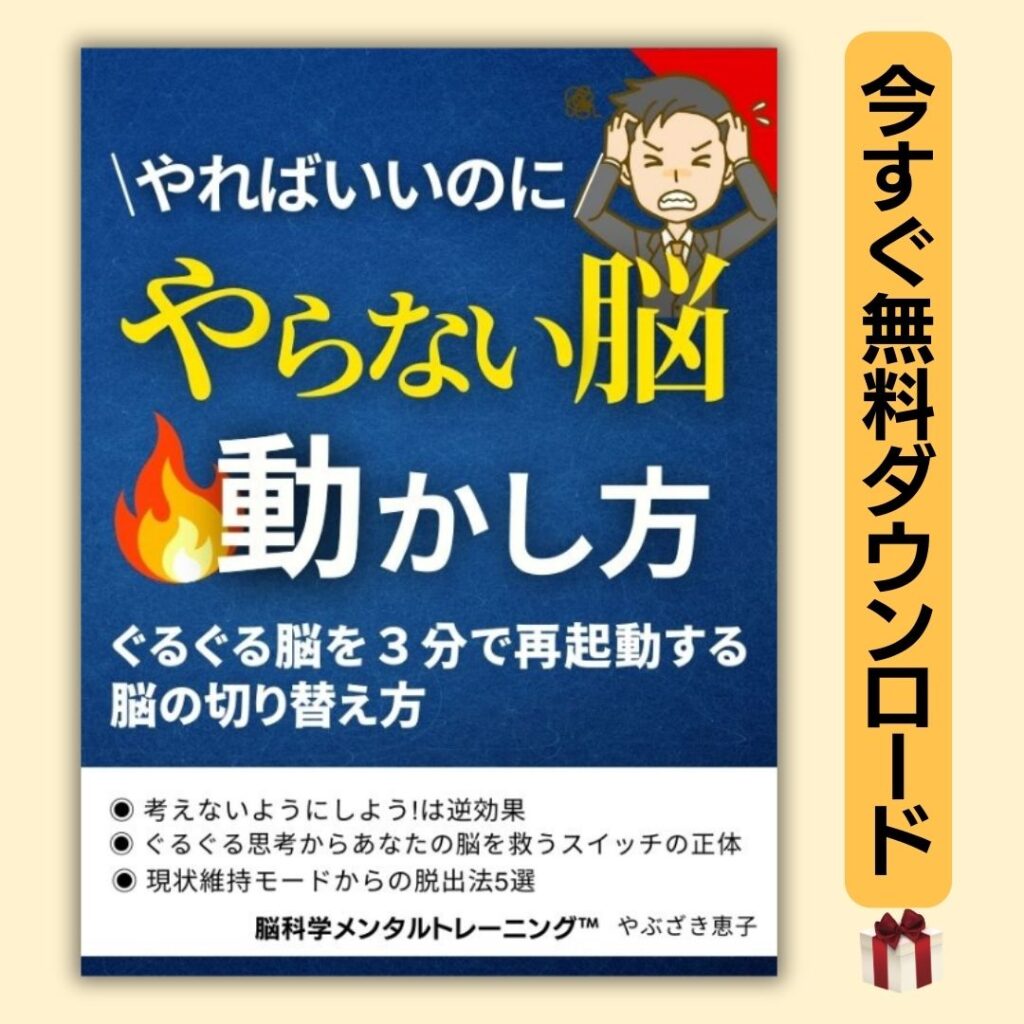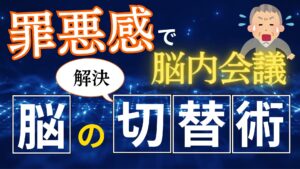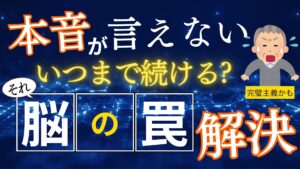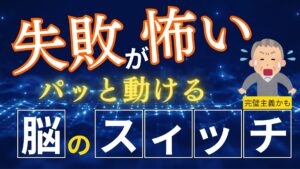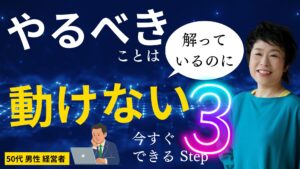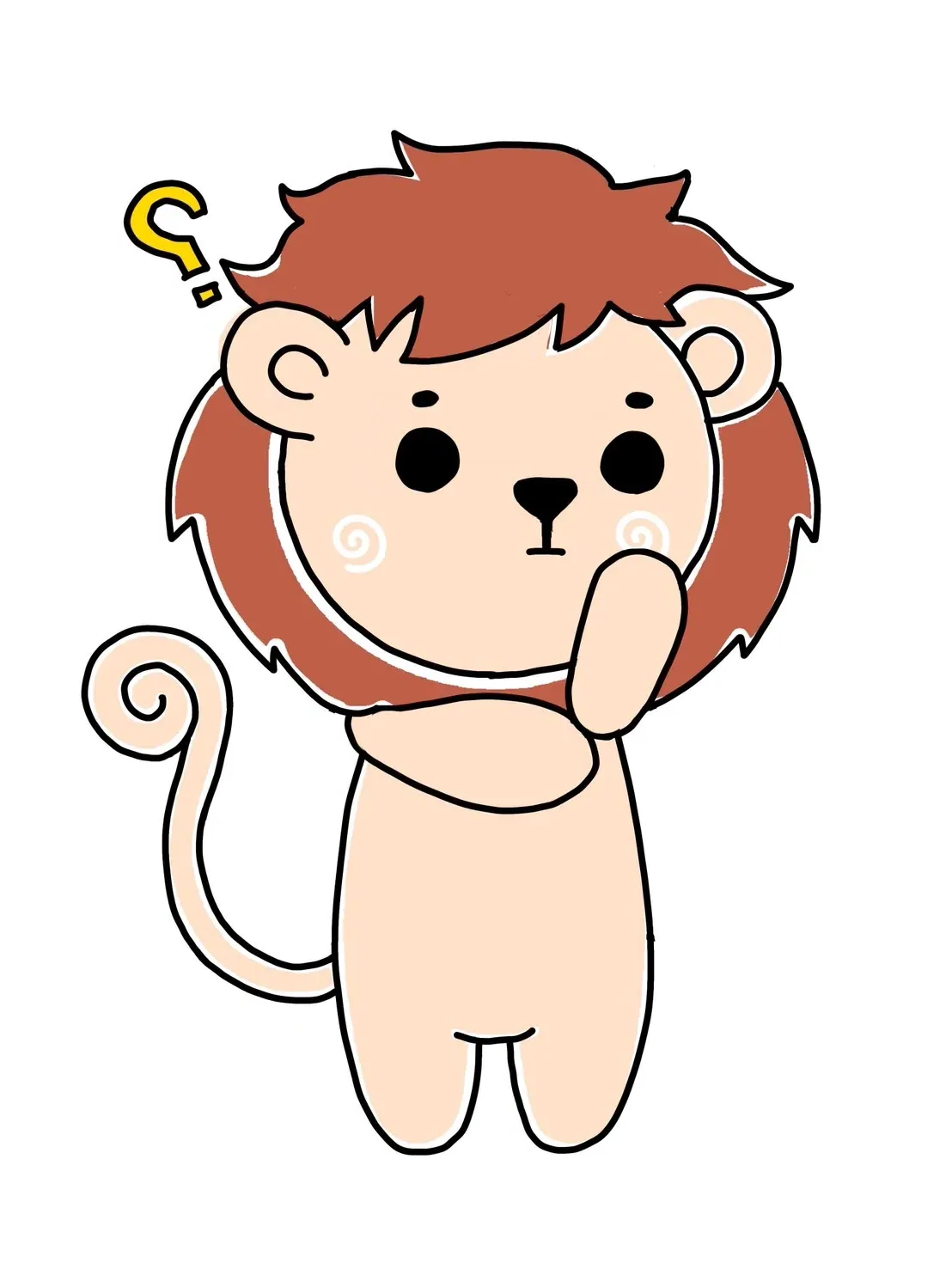 メンタくん
メンタくん正直、やる気はあるんですよ…。
だけど毎回“もっと完璧にしなきゃ”って思ってるうちに、手が止まってしまって…結局また自己嫌悪。
『自分って、結局ダメなのかな』って思うんです。



それ“脳の防衛反応”なんです。
完璧を求めすぎると、脳は“失敗のリスク”を避けようとして、無意識にブレーキをかけるんですよ。
つまり、“失敗を避けるために、あえて動かない”という反応なんです。
これは性格ではなく、脳のしくみの問題なんです。
この記事のハイライト
・完璧を求めすぎることは、「無意識の脳のクセ」であり、あなたを苦しめる思考パターンのひとつ。
・必要なのは、“意志の強さ”ではなく「強さの質」を変える視点。
・脳は“失敗のリスク”を避けようとして、やる気を抑え、「動かない選択」をしてしまう。
・完璧主義の人がハマりやすいのは、中途半端・比較・恐れ・自己否定という4つの行動停止パターン。
・行動できるようになるカギは、脳のしくみに合った3つの習慣を取り入れること。
・行動できないのは意志の弱さではなく“脳の働き”のせい。脳を整えれば、行動は変えられる。
完璧を求めすぎて動けないのは“脳のクセ”。整えれば、行動できる自分を取り戻せる



やらなきゃとは思っている。だけど、なぜか動けない。
それは
あなたの意志や能力の問題ではありません。
むしろ、責任感が強く
結果を出し続けてきた人ほど陥りやすい
“脳のクセ” が原因です。
特に50代の管理職は
「失敗は許されない」
「常に正解を出さなければならない」
という目に見えないプレッシャーを
誰よりも背負っています。
その重圧に反応した脳
“完璧じゃないなら、やらないほうがいい” と
無意識にブレーキをかけてしまう
これが、動けなくなる正体です。
ですが、脳には“仕組み”があります。
だからこそ、そのクセに気づき
少し整えていくことで、行動は変えられます。
「完璧を求めすぎる」とは何か?その特徴と心理のしくみ
完璧を求める人ほど
「もっと努力すればできるはず」と
“意志の強さ”で乗り切ろうとします。
けれど、それでも動けない──
そんなとき必要なのは
“意志の強さ”ではなく
”強さの質”を変える視点です。
本当の強さとは
自分を追い込むことではなく
脳が安心して動ける環境を整える力のこと。
では、なぜその「安心できる環境」を
持てないのでしょうか?
それは、無意識に高すぎる基準や
プレッシャーの中で行動しようとしてしまうからです。
特に50代の管理職には「これくらい当然」と
自ら決めた高い基準を
あらゆる場面に当てはめる傾向が見られます。
その背景にあるのは
失敗は許されない
無能と思われたくない
という強い不安。
これは、長年の経験や立場から培われた
「勝ち続けなければ価値がない」という思い込み
による影響が考えられます。
その結果
自分を労わる余裕がなくなり
本来の自信や安心感も揺らいでいきます。
そして気づけば
「能力はあるのに動けない」状態に──。
この思考は意志の弱さではなく
脳の防衛反応。
まずは「自分に厳しすぎる」ことに気づくことが
“行動できる脳”を取り戻す第一歩です。
「完璧を求めすぎる脳」が行動を止めるメカニズムとは?


脳は「失敗のリスク」を察知すると
やる気があっても
無意識に“動かない”選択をしてしまいます。
50代の管理職になると
「もう失敗できない」
「周囲からの評価を落としたくない」
といった思いが強くなりがちです。
その緊張状態が続くことで
脳は**常に“危機管理モード”**になります。
「まだ不十分かもしれない」
「今やると失敗するかも」
そんな判断が脳内で下されると
ストレスホルモン(コルチゾール)が分泌され
自然と行動が抑えられてしまうのです。
つまり、あなたの意志が弱いわけではなく
脳が「今は動くな」と判断しているだけなのです。
この仕組みを知るだけでも
「なぜ動けないのか」が腑に落ちて
少しずつ
“動ける自分”を取り戻すきっかけになります。
豆知識:コルチゾールは“逃げる・隠れる”などの防衛行動を優先させる働きがあり、
思いきって動く力(実行機能)を一時的に弱める作用があります。
「完璧を求めすぎる人」が陥りやすい4つの“行動停止”パターン
「やらなければいけないのに、なぜか動けない」
その背景には
脳が無意識にブレーキをかける4つのパターンが
隠れていることがあります。
1. 中途半端で終わる
「完璧に仕上げなければ」と構えすぎて
一歩目が重くなる。
締切間際にようやく手をつけても納得できず
途中で手が止まる──
そんな悪循環に陥っていませんか?
2. 比較して落ち込む
実績があるはずなのに
若手の成果や周囲の評価が気になる。
本来比べる必要のない相手と比べ
自分を必要以上に低く見積もってしまう。
それは、長年の責任感の裏返しでもあります。
3. ミスが怖くて着手できない
「失敗できない」という思いが強く
準備ばかりで動けなくなる。
注目される仕事ほど
「完璧じゃないと出せない」と考えてしまい
結果的に行動が後回しになります。
4. 自己否定・疲弊感
理想が高いからこそ
「今の自分じゃダメだ」と感じてしまう。
表向きは冷静でも、内心では疲れ果て
エネルギーを消耗し
気力さえ奪われていきます。
これらのパターンは
**怠けや能力不足ではなく
脳があなたを守ろうとする“防衛反応”です。
つまり、問題は性格ではなく
「脳の仕組み」にあるのです。
完璧を手放して“行動できる脳”をつくる3つの習慣


ここで紹介する3つの習慣は
どれも“がんばらなくていい脳の整え方”です。
習慣①:合格ラインを「80点」に決めておく
完璧を目指すほど、脳は動けなくなります。
あらかじめ「80点で合格」と決めておけば
脳が「これで大丈夫」と判断し
一歩目が軽くなります。
例:
・ プレゼンは“伝わる”を優先し、細部は後回し
・部下への指示も、まず方向性だけ伝える
仕事は、動き出せば自然に進みます。
完璧は後で整えれば十分です。
習慣②:「If-Then」で脳のスイッチを自動化する
脳は、判断するたびにエネルギーを消耗します。
だからこそ、「○○したら△△する」という
ルールを決めておくと、行動が自動化されます。
例:
・コーヒーを飲んだら、今日のタスクを5分だけ書き出す
・出社したら、まず報告メールだけ返信
ポイントは、気合い不要の小さな行動にすること。
やる気に頼らず、ムダなエネルギーを減らせます。
習慣③:「もし失敗するとしたら?」と最初に考えておく
脳は不安を感じるとブレーキをかけます。
だから、不安をあらかじめ“つぶしておく”と
行動しやすくなります。
これは「プレモーテム思考」と呼ばれる方法で
最悪を想定して備えるというものです。
例:
・資料で質問されそうな部分に補足資料を用意しておく
・時間が足りないときは、A案だけに集中する
「失敗しても大丈夫」と脳が判断できれば
自然と動きやすくなります。
どの習慣も
“やる気に頼らず脳が安心して動ける状態”
を整えることが目的です。
自分を変えるのではなく
脳に合ったやり方に切り替えていきましょう。
「動けなかった自分」を変えた50代管理職のリアルな声
実際に、「完璧を求めすぎて動けない」状態から抜け出した
50代の方々の声をご紹介します。



完璧主義で手が止まり、いつもギリギリで自己嫌悪。
「脳の反応だった」と知って気がラクに。
今では“80点でOK”と決めて、早めに動けるようになりました。



「まだ完璧じゃない」と悩み続け、心も体も疲弊。
脳がブレーキをかけていたと知って安心しました。
優先順位を決め、小さな行動から始める習慣がついてきました。



ミスや失敗に過敏で、自分を責め続けていました。
今は「まず動いてみよう」と考え方が変わり、
行動量が増えて、気持ちも前向きになっています。
まとめ ― 完璧を目指すよりも、一歩動ける自分を取り戻す


「やらなきゃとは思っている。だけど、なぜか動けない。」
それは、あなたの意志の弱さでも
能力の問題でもありません。
脳があなたを守ろうとしている
ごく自然な反応です。
今回紹介した3つの方法は
無理なく行動を取り戻すための “脳の整え方” です。
行動を取り戻す3つの習慣
・「80点で十分」と決めることで、最初の一歩が軽くなる
・「○○したら△△する」ルールで、迷いを減らす
・「もし失敗するとしたら?」と事前に備えることで、脳に安心を与える
これらは、自分を責めて変えようとするのではなく
脳が自然と動ける環境を整えるアプローチです。
完璧を求めて立ち止まるよりも
まず一歩、動ける自分を取り戻すこと。
そして、その一歩が重なっていくことで
50代のあなたの経験が
再び“力として活きる道”が見えてきます。
もし今
「自分を責めるクセがやめられない…」
「頭の中がグルグルして疲れる…」
そんな状態に心当たりがあるなら
脳のケアが必要なサインかもしれません。
そんなあなたへおすすめの小冊子があります。
👉【小冊子】 自責癖と脳疲労の関係を明らかにして グルグル悩む時間をゼロにする
脳科学メンタルセルフカウンセリング方法
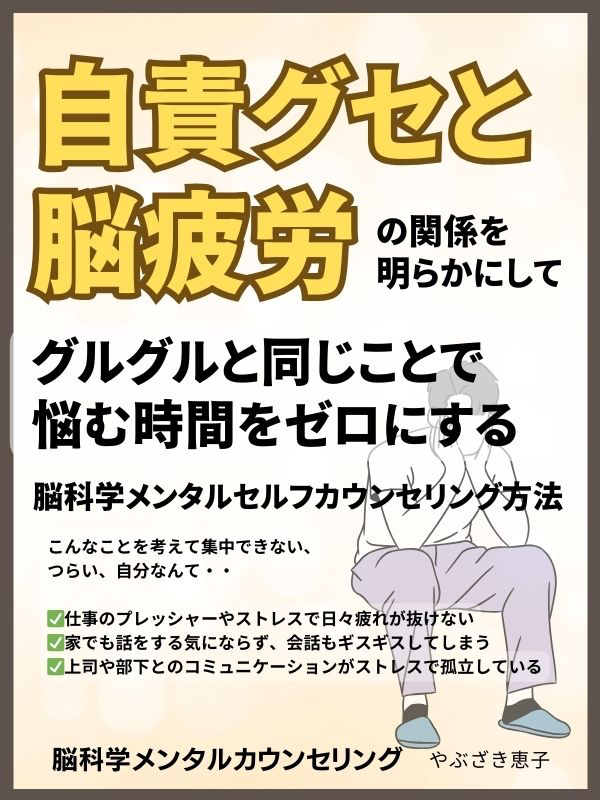
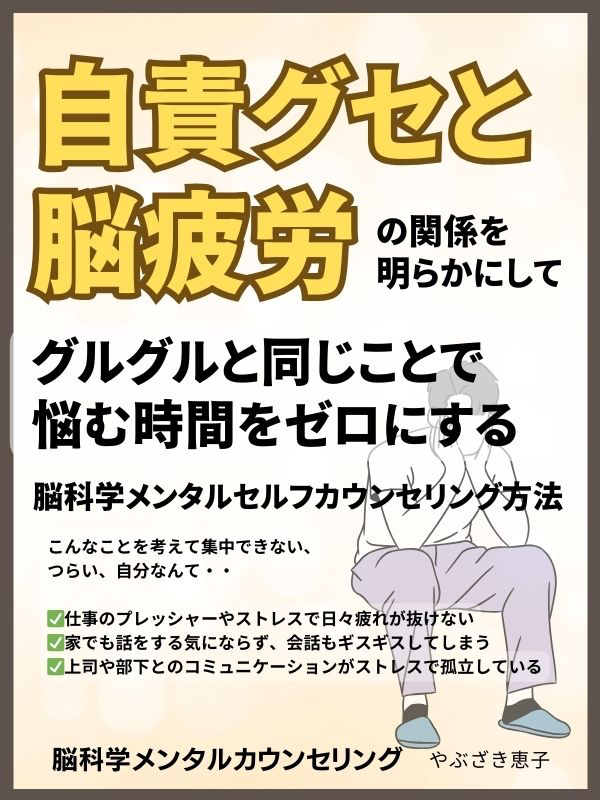
脳の疲れと自責グセの関係を、わかりやすく解説しています。
「気づくこと」が、脳を変える第一歩です。
ぜひ、あなたの次の一歩にお役立てください。
よくある質問(Q&A)
- 完璧を求めすぎるとどうなりますか?
-
脳が“常に危機モード”になり、行動が止まりやすくなります。
完璧を求めると、脳は「失敗してはいけない」と認識し
**ストレスホルモン(コルチゾール)**を分泌します。
この状態が続くと、脳は“リスク回避”を最優先し
やる気や判断力を一時的に低下させるのです。特に責任ある立場の方ほど、「もう間違えられない」という心理が強く
脳が**“守り”に入ってブレーキをかける反応**が出やすくなります。 - 完璧を求める人の特徴は?
-
自分に対して非常に厳しく、妥協ができず、「常に最善を尽くさねば」と考えがちです。
具体的には以下のような傾向があります
・小さなミスでも強いストレスを感じる
・他人の評価に敏感で、自分を比較しやすい
・準備に時間をかけすぎて、実行が遅れる
・成果が出ても「まだ足りない」と感じるこれらは、脳が“安心”よりも“リスクの最小化”を優先している証拠でもあります。
- 完璧主義の人はうつになりやすいですか?
-
はい。完璧を求め続ける思考は、脳に慢性的なストレスをかけ続けるため、結果としてうつになりやすい傾向があります。
「失敗してはいけない」「きちんとやらなければ意味がない」といった思考が続くと、
脳は常に緊張状態となり、リラックスできなくなります。この状態が続くことで、気分を安定させるセロトニンや、やる気を生み出すドーパミンなどの脳内ホルモンが減少し、活力や意欲が低下。
その結果、心が疲れ果ててしまいやすくなるのです。特に50代以降は、回復力やストレス耐性の変化も影響し、
これまでと同じ頑張り方では、知らないうちに心が疲れ、うつ状態に近づくリスクが高まります。 - 完璧主義から抜け出す方法はありますか?
-
はい、「考え方」ではなく「脳の反応」を整えることがカギです。
「もっと頑張らなきゃ」「まだ不十分だ」と感じるのは、意志が弱いからではなく、
脳が“失敗を避ける”ためにブレーキをかけている反応です。脳には「可塑性(かそせい)」という性質があり、習慣や刺激によって働き方が変わります。
つまり、脳にやさしい習慣を取り入れるだけで、完璧にこだわって動けない状態から抜け出せるのです。
脱・完璧主義におすすめの3ステップ・「80点で出す」と決める
→ 「ここまでで良し」と線引きすれば、脳のプレッシャーが軽くなり動きやすくなります。
・「○○したら△△する」とルール化
→ 例:「デスクに座ったら、まず会議資料に目を通す」など、迷いを減らす仕組みをつくる。
・「どこでつまずくか」を想定して備える
→ 補足資料の用意や優先順位の決定など、“もしもの準備”で脳に安心感を与えます。自分を責めるのではなく、脳の仕組みに合った整え方をする。
それが、完璧主義から自由になり、行動できる自分を取り戻す第一歩です。