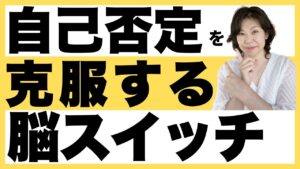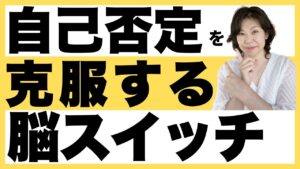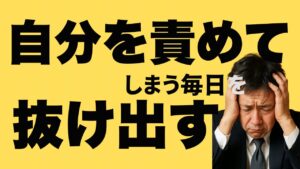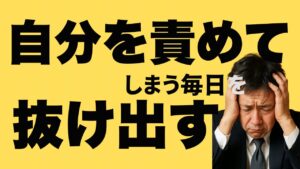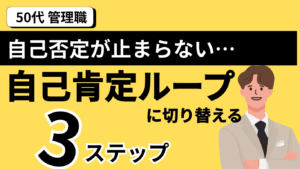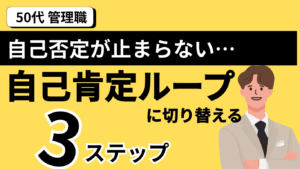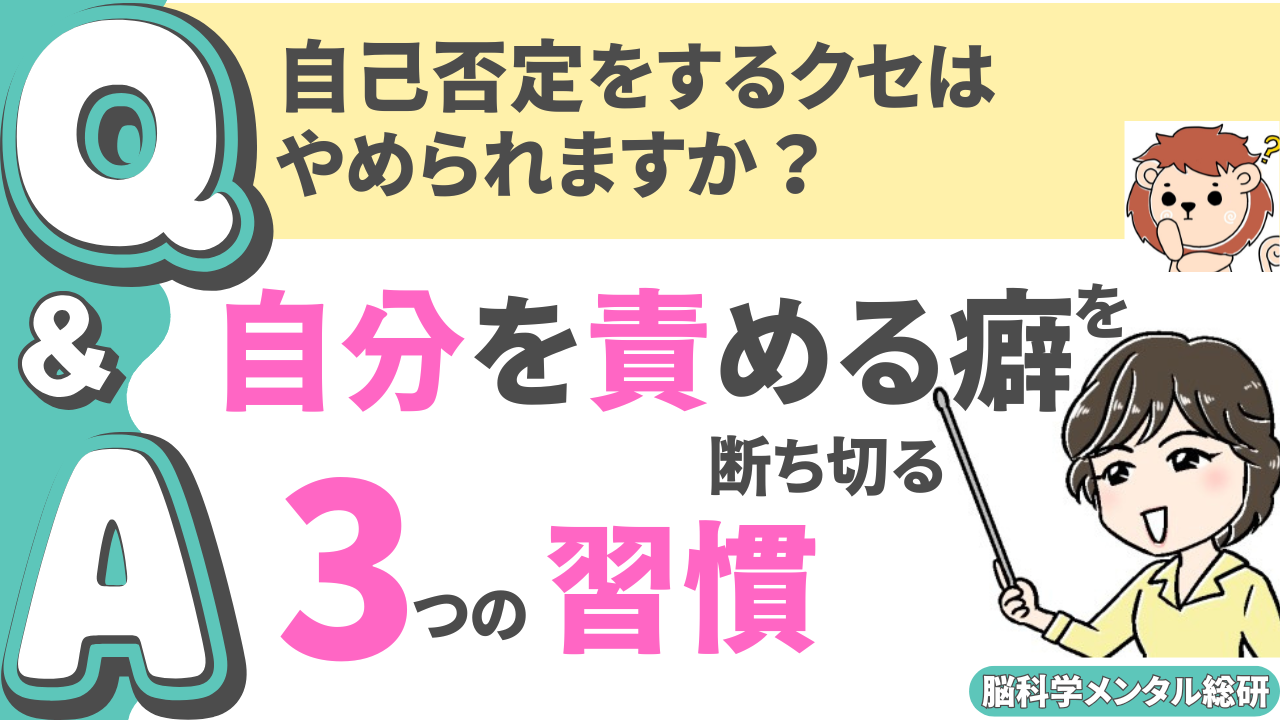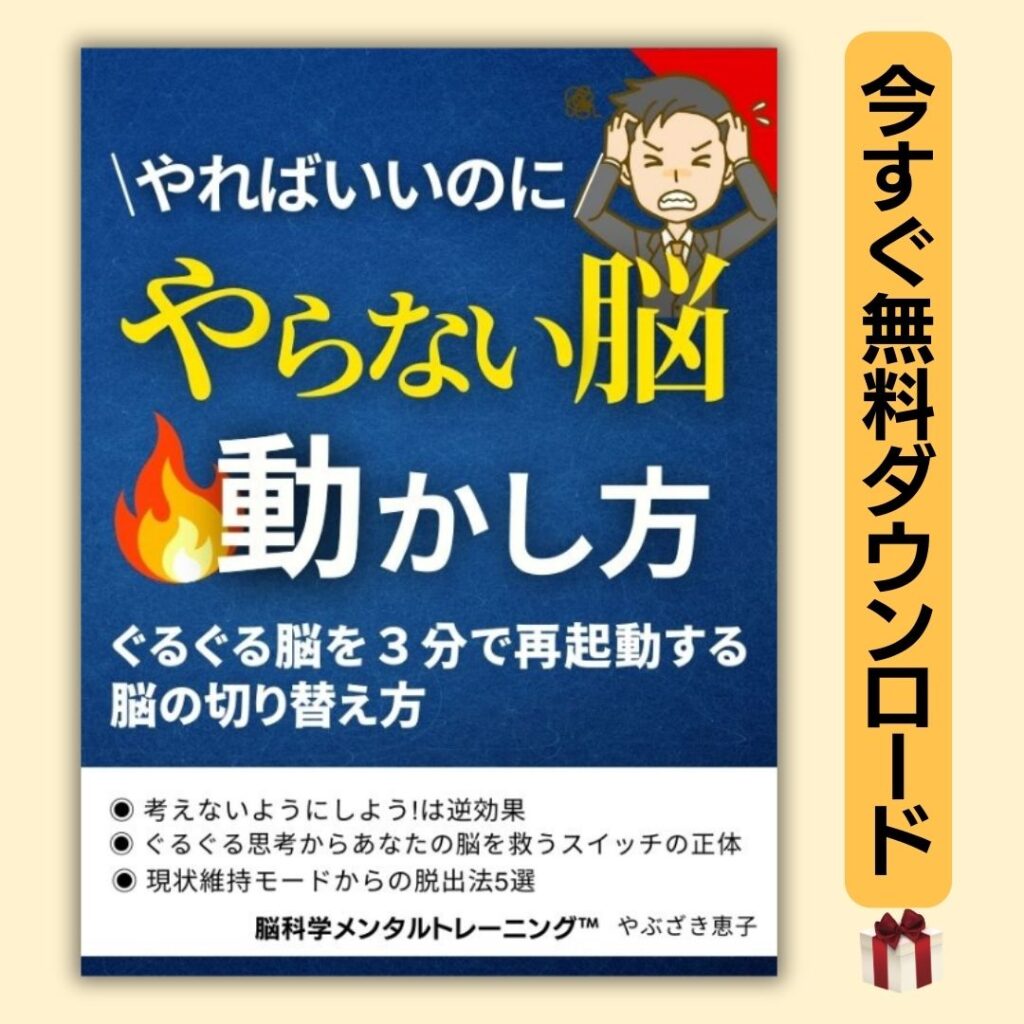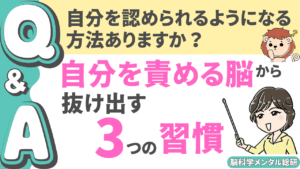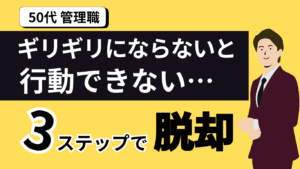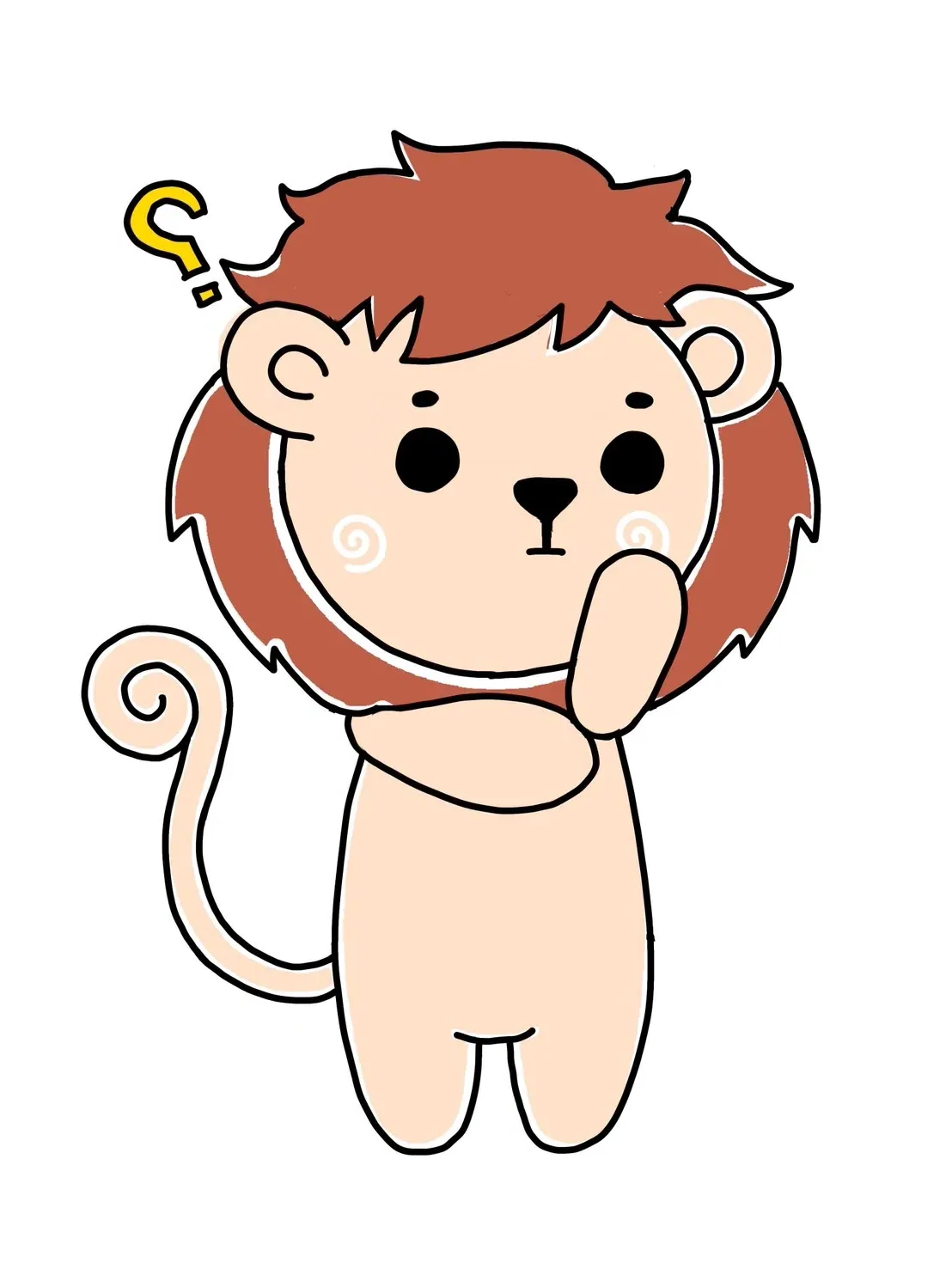 メンタくん
メンタくん会議で思うような成果を出せなくて“自分は管理職に向いていないんじゃないか”“他の人ならもっと上手くやれただろうに”と、気づけば自分を責めることばかり。
頭の中でぐるぐる考えが止まらなくなって、正直しんどい。
こんな“自分を責めるクセ”、 本当にやめられるんですか?



もちろん、やめられますよ。
自分を責めてしまうのは“意志の弱さ”や“性格のせい”ではなく、脳のクセがそうさせているんです。
脳の仕組みを整えれば、そのぐるぐる自己否定ループを断ち切って
“自分を認められる回路”に切り替えることができるんですよ。
この記事のハイライト
・ 自己否定は「性格の弱さ」ではなく、脳のクセがつくった思考習慣にすぎない
・ 自己否定が続くと、会議やプレゼンで自信を失い、成果が出にくくなる悪循環に陥りやすい
・ 3つの習慣で脳を整えれば、「自分を責めるクセ」から抜け出し、管理職としてのパフォーマンスも高められる
・大切なのは「最初の一歩」。小さな習慣を始めることで、脳は「責める回路」から「認める回路」へ切り替わり、部下や周囲からも信頼される自分に変わっていく
なぜ自己否定を繰り返してしまうのか?


自己否定をやめたいと思っても
気づけば同じ思考に戻ってしまう…
それは「意志が弱いから」ではなく
脳のクセに原因があります。
脳は本来、危険を回避するために
「失敗」「不安」「批判」といった
ネガティブ情報を優先的に記憶する仕組みを
持っています。
そのため



会議でうまく進行できなかった



成果が出なかった
といった体験が強く残り
頭の中で何度も再生されてしまうのです。
こうして「失敗した=自分がダメだ」
という思考が習慣化し
自己否定の回路が固定されていきます。
自己否定が続くとどんな悪循環に陥る?
自己否定が習慣化すると
次のような悪循環に陥りやすくなります。
✔うまくいかないとすぐに「自分の責任だ」と過剰に背負い込む
✔萎縮して会議で意見が出せなくなる、決断が遅れる
✔成果が上がらず、さらに自信を失う
✔「やっぱり自分は管理職に向いていない」と思い込む
このスパイラルに陥ると
パフォーマンスだけでなく心身にも影響が出てきます。
「眠りが浅い」
「集中力が続かない」
「休日も気が休まらない」
管理職世代によく見られるサインとして
現れることも少なくありません。
自己否定をやめると問題解決力が高まる!|リサーチャーみすずの体験談


自己否定をやめると
問題解決力そのものが高まる――
私はそのことを
自分自身の体験を通して強く感じています。
正規職員として働きながら
脳科学メンタル総研のリサーチャーとして
執筆活動を始めて1年以上になります。
以前は職場で自己否定ばかりしていましたが
今ではほとんどなくなりました。
それについては、こちらの記事
自己否定が止まらない管理職へ:自己否定ループから自己肯定の回路へ変わる3ステップ
に書きました。
ただ、リサーチャーとして活動を始めた当初は
記事を書くことに大きな壁を感じました。



記事をかくなんて私には無理だ…
こんな私なんて必要とされていない
そう思い込み
自己否定のループに陥りかけたこともあります。
そんなとき役立ったのが
感情を書き出すことでした。
「落ち込んでいる」
「不安だ」
「焦っている」と書くだけで
気持ちを客観的に見られるようになり
冷静さが戻ってきます。
すると
「私にはむりだ」
⇓
「始めはできなくて当たり前。できるようになるために学んでいるところ」
と、思考を切り替えられるようになりました。
今でも自己否定が顔を出すことはあります。
ですが、私は「切り替えられる自分」を知っています。
私は脳科学に基づいた方法を学び
実践を重ねてきました。
その結果、目の前の悩みを解決できるだけでなく
問題解決力そのものが高まってきている。
そう感じています。
おかげで、仕事に向き合う姿勢も
以前よりずっとラクになりました。
そしてこれは、管理職の方々にも
同じように役立つはずです。
一度自己否定をやめられるようになると
目の前の課題を解決できるだけでなく
問題に向き合う力が強化され
仕事への姿勢もラクになります。
その結果、冷静に判断しながら成果を出し
部下からの信頼を積み重ねていけるでしょう。
今日から始めよう!「自己否定をやめる3つの習慣」
自己否定をやめるのに
特別な努力や才能はいりません。
脳のクセを整えるための小さな習慣を
今日から取り入れてみましょう。
1.感情に名前を付ける(感情のラベリング)
「悔しい」「不安だ」「情けない」など
自分が感じている感情に名前を付けてみましょう。
言葉にすることで
感情は客観的に見えるようになり
思考のぐるぐるから抜け出しやすくなります。
感情のラベリングとは
感情に名前を付けると、脳が落ち着きやすくなることが研究でわかっています。
アメリカの心理学者マシュー・リーバーマン博士の実験では、「不安だ」「イライラしてる」と言葉にするだけで、ストレス反応が和らぎ、冷静さを取り戻せると示されています。
2.鎖骨タッチ×目線ワークで脳を整える
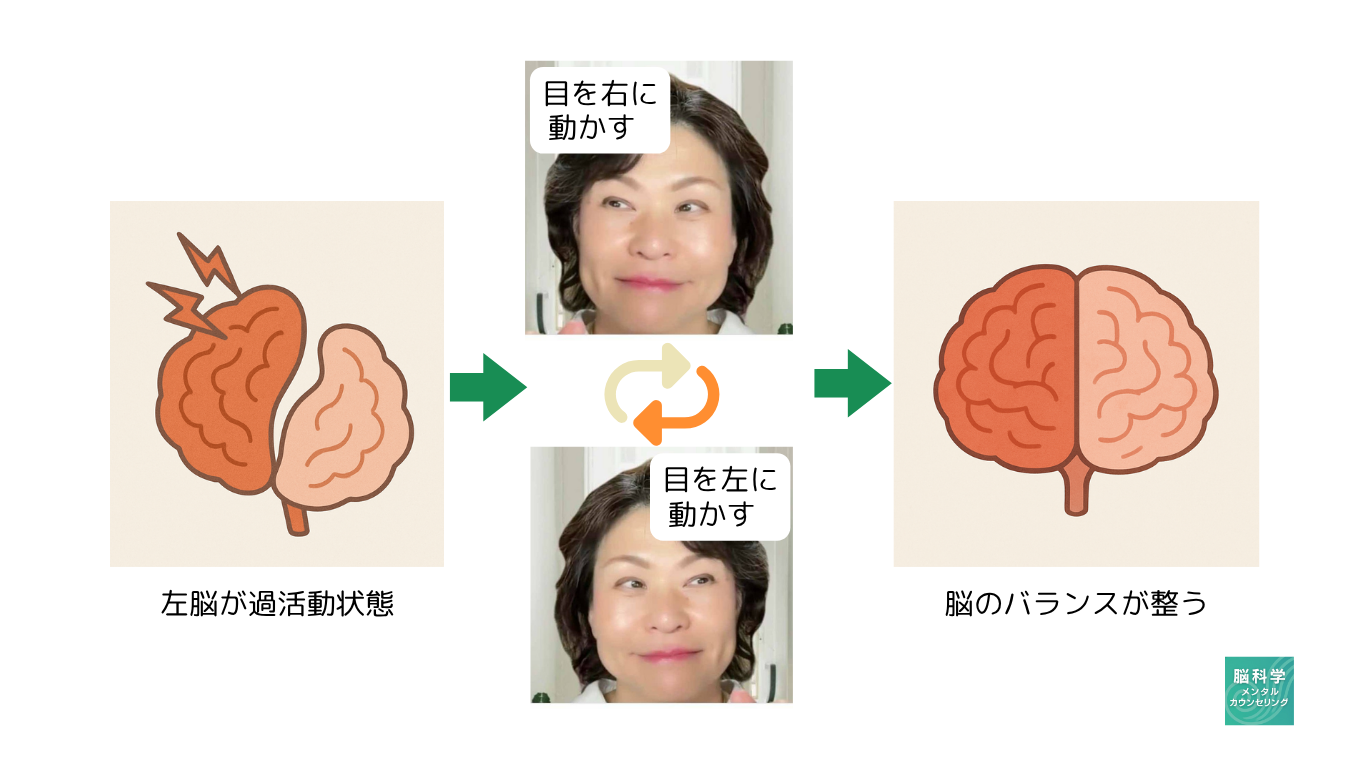
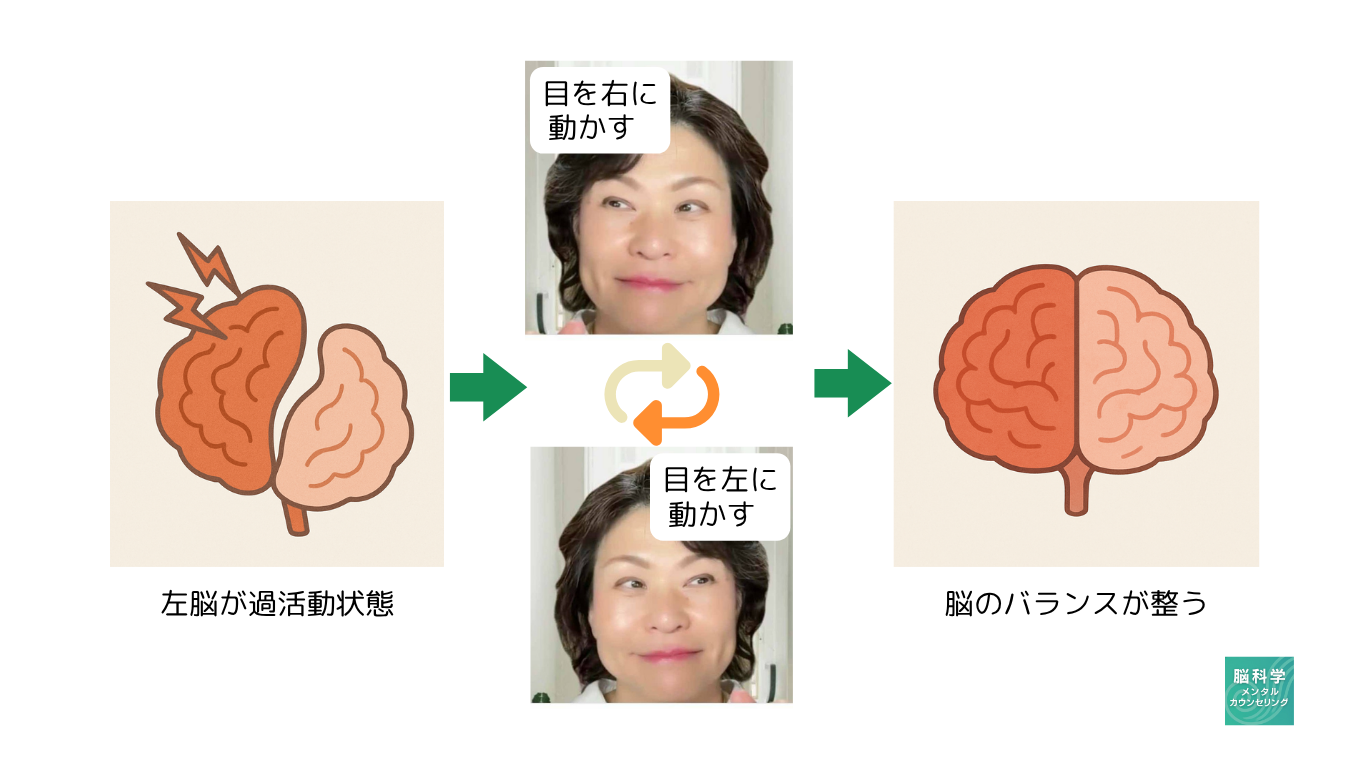
鎖骨の下を軽くさすりながら深呼吸をして
目を左右にゆっくり動かしましょう。
2〜3分で十分です。
右脳と左脳の働きが整い
頭の中の「ぐるぐる思考」が落ち着き
不安をリセットできます。
3.小さな達成に“〇”をつける
一日の終わりに「今日できたこと」を振り返り
“〇”をつけましょう。
・部下の提案を最後まで聞けた
・資料を予定通りに提出できた
・会議で建設的な質問を投げかけられた
小さな達成を記録すると
脳は「自分はできている」
という感覚を強化します。
このとき分泌されるドーパミンが
やる気を後押しし
自信を積み重ねていけるのです。



“リーダーなのに成果を出せず『無能』なんじゃないか・・・”
“他の人がやればもっと上手くできたのでは…”
と落ち込んでいましたが
3ステップを実践したら
“いちいち否定しなくてもいい”
“落ち込む必要なんてない”
と自己否定しなくなったんです。
まとめ:自己否定から自己肯定へ|最初の一歩を踏み出そう


自己否定は
性格や努力不足の問題ではなく
脳のクセによって繰り返される思考習慣です。
だからこそ、脳を整えることで
「自分を責める回路」を「自分を認める回路」へ
切り替えることができます。
管理職に求められるのは、迷わず決断し
部下を導く冷静さと自信。
その自信は、小さな習慣を取り入れることで
少しずつ取り戻せます。
そしてその一歩が、あなたを
“ぐるぐる自己否定”から抜け出し、自己肯定できるリーダー” へと
近づけてくれるはずです。
さらに実践的な方法を知りたい方にお勧めしたいのが。
👉 『ネガティブ思考をサッと切り替える脳スイッチの押し方』
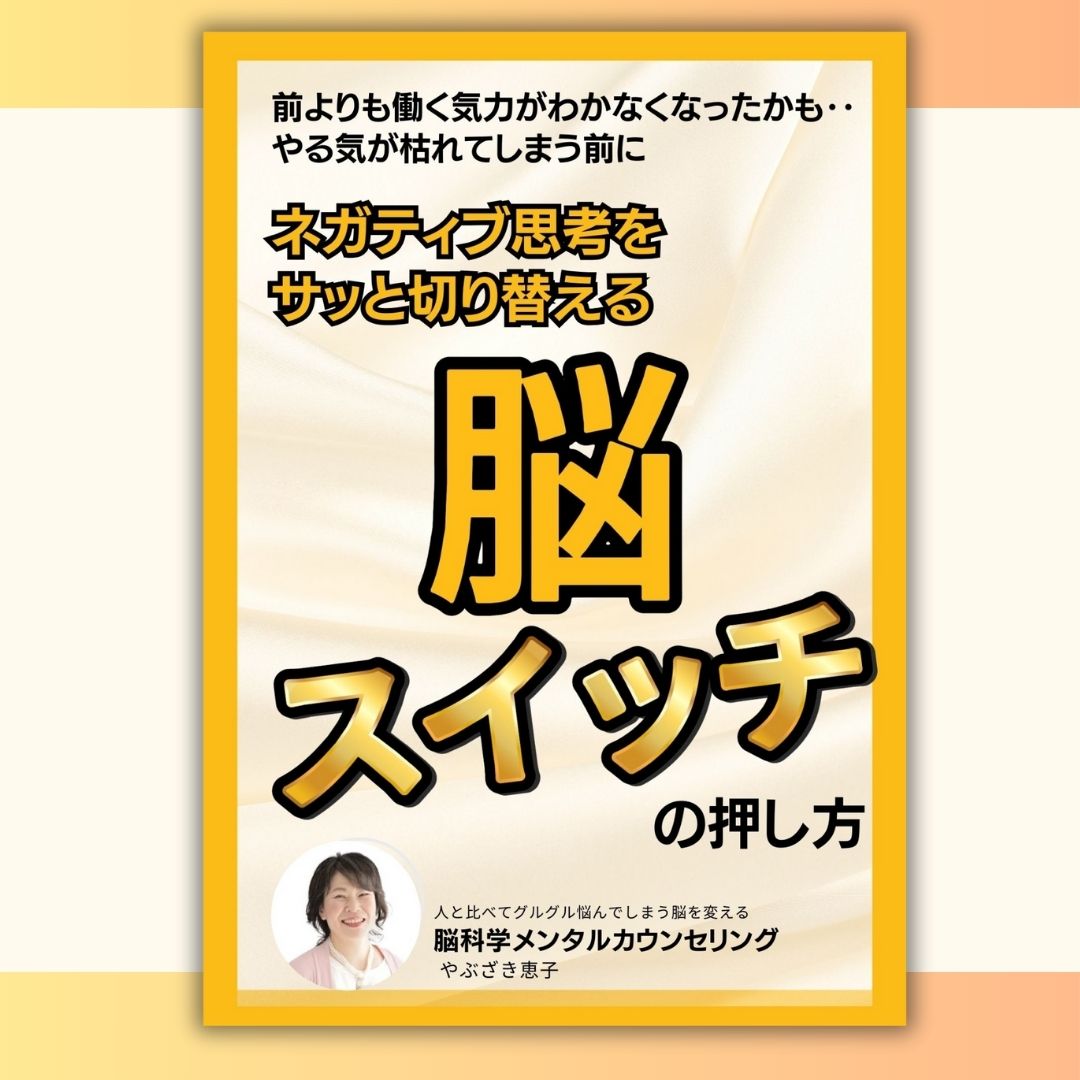
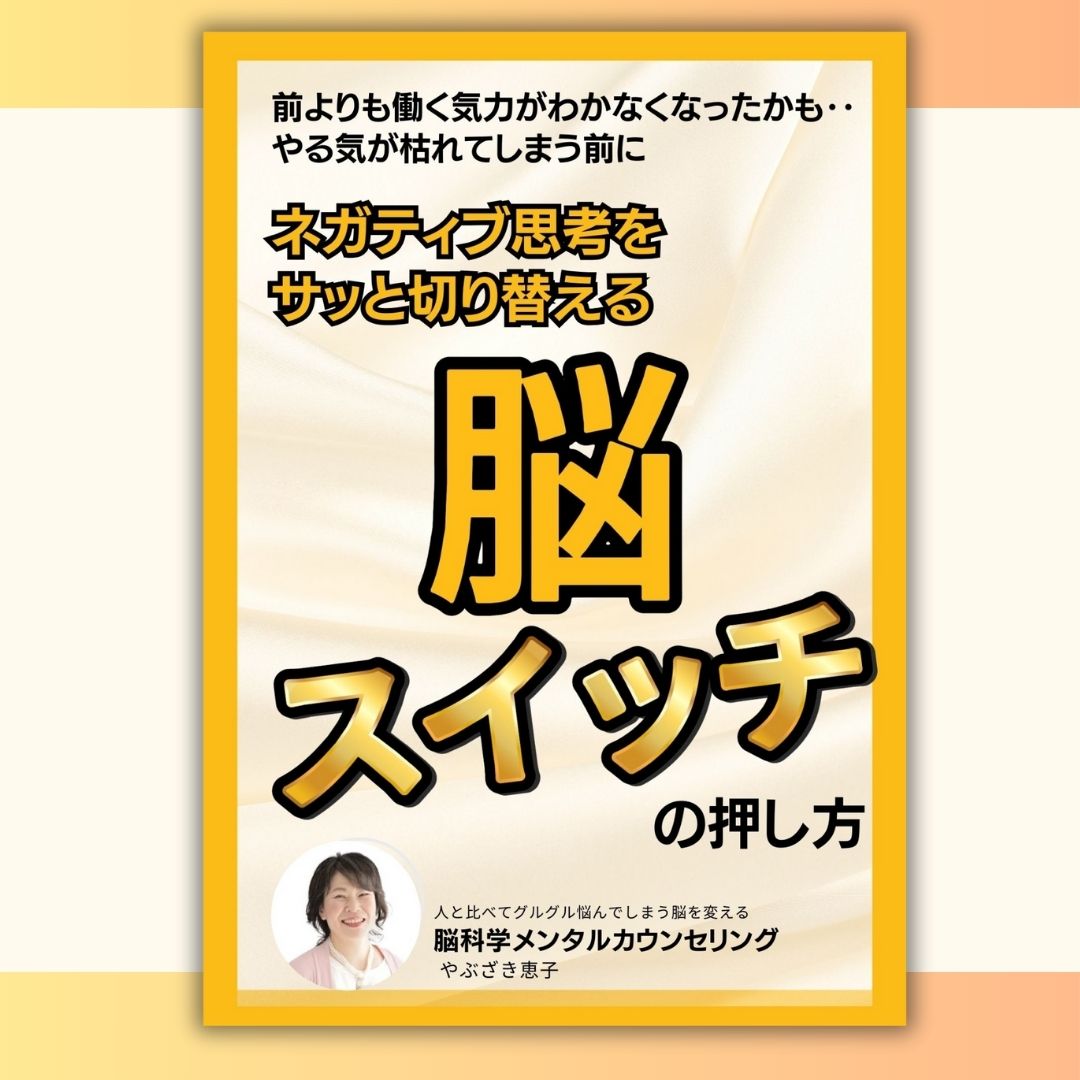
この一冊では、自己否定のぐるぐるを和らげ
思考回路を切り替えるための具体的な方法を
わかりやすく紹介しています。
脳が変われば、仕事の成果も人間関係も変わります。
一歩を踏み出して
「自分を責める上司」から、部下に信頼される
「自己肯定できるリーダー」 へと変わっていきましょう。
よくある質問Q&A
- 自己否定をやめる方法はありますか?
-
あります。自己否定は「意志の弱さ」ではなく、脳のクセによる思考習慣です。
やめるには
①感情に名前を付ける(ラベリング)
②鎖骨タッチや深呼吸で脳を落ち着ける
③小さな達成に〇をつける
といったシンプルな習慣が有効です。
こうした習慣を積み重ねることで
脳は「責める回路」から「認める回路」へ少しずつ切り替わっていきます。 - 自己否定のクセを直すには?
-
自己否定のクセを直すには、「脳の習慣の書き換え」が必要です。
脳は失敗や不足を優先的に記憶するため、そのままでは自己否定が強化されやすいのです。
そこで「できたことを記録する」「感情を言葉にする」といった小さな行動を意識的に続けると
新しい回路が育ち、自己否定に流されにくくなります。 - 自己否定をやめると部下との関係はどう変わりますか?
-
自己否定が減り、上司自身が冷静さを保てるようになると、感情的な叱責が少なくなります。
その結果、部下は安心して意見を出しやすくなり、信頼関係が築かれます。
上司も自信を持って対応できるため、チーム全体の成果にもつながります。 - 50代以降でも自己否定をやめられますか?
-
はい。脳は年齢に関係なく「変化する力(可塑性)」を持っています。
新しい習慣を意識的に取り入れることで、
50代からでも「自分を責める回路」を弱め、「自分を認める回路」を育て直すことができます。
遅すぎるということはありません。 - 管理職として責任が重いと、どうしても自己否定に陥ります。責任感とどう両立すればいいですか?
-
責任を果たすことと自己否定は別です。
責任は「課題に取り組む姿勢」であり、自己否定は「自分を攻撃する思考」です。
脳を整える習慣を持つことで、責任感を保ちながらも冷静に課題に向き合えるようになり、
過度な自己否定に振り回されなくなります。
おすすめの関連記事